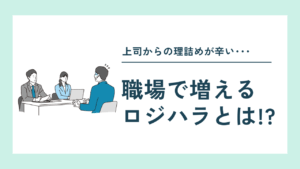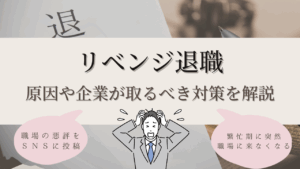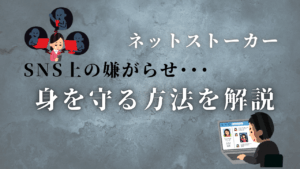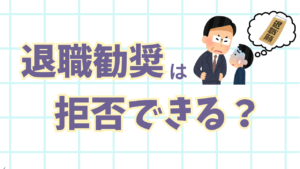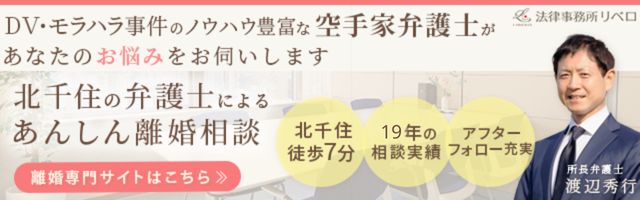
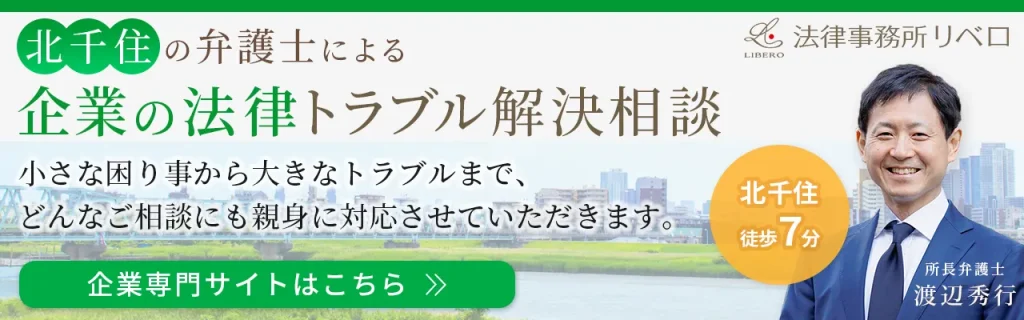
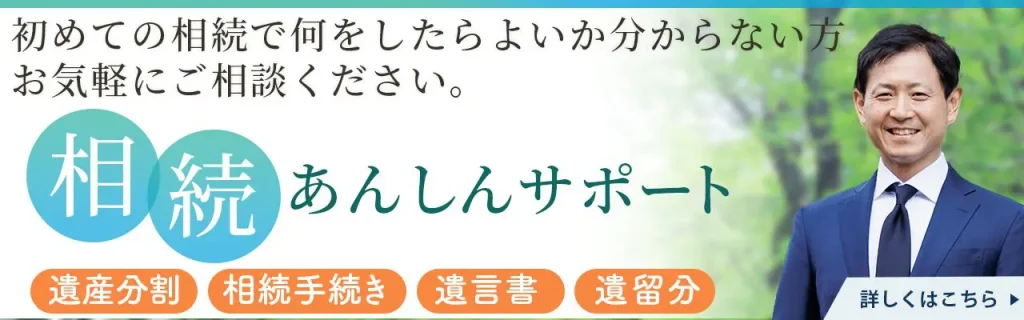
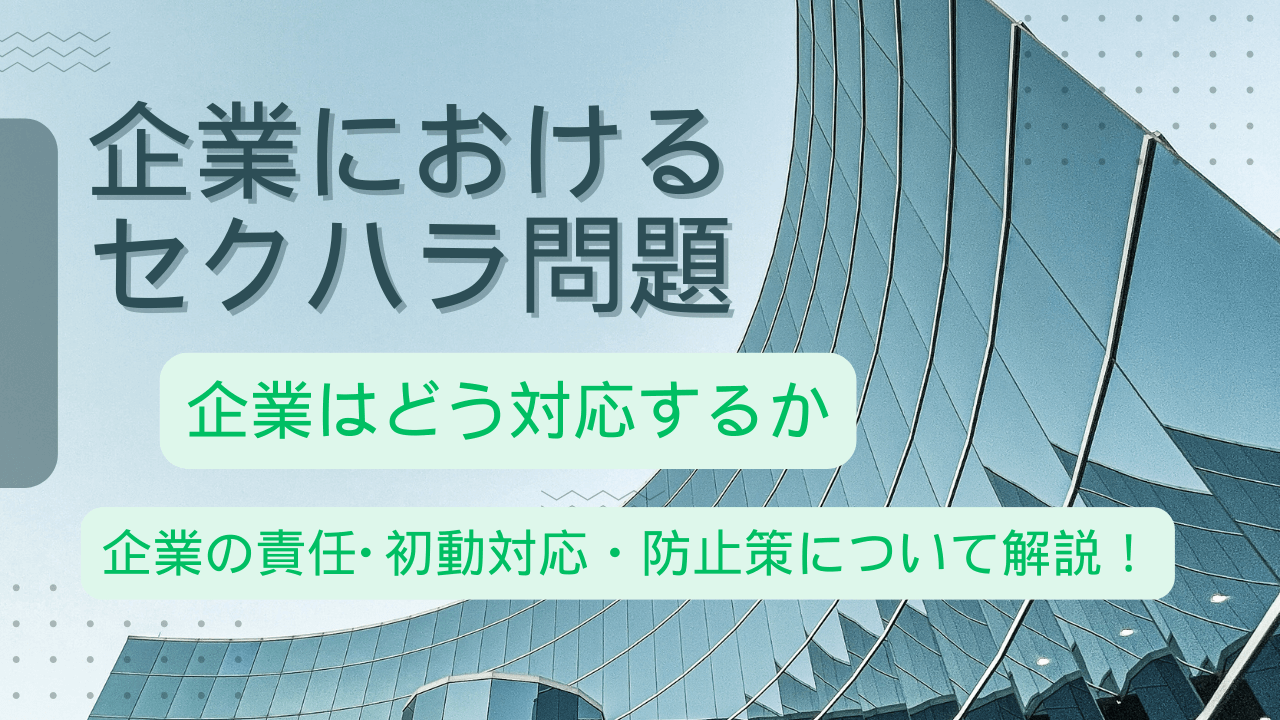

法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
近年,職場におけるセクシュアルハラスメント(セクハラ)問題は,企業の信頼性や社会的責任を問う重大な課題となっています。
本記事では,セクハラが発生した際の企業の責任や初動対応,再発防止策まで,実務に役立つ視点から解説します。

こちらのコラムは,職場におけるセクハラについてどのような言動がセクハラに該当するのか,なぜセクハラがおこるのかを詳しく解説していますので,ぜひ併せてご覧下さい。

以前は個人間のトラブルとみなされがちだったセクハラも,現代では企業が組織的に対応すべき問題として捉えられるようになりました。
これは,社会全体の人権意識の高まりや,職場の多様性が進んだことによるものです。
たとえば、国際的な#MeToo運動をきっかけに,被害を訴える声が可視化され,「沈黙していた側」が声を上げやすい社会的雰囲気が生まれました。
このような背景により,企業のハラスメント対策は“社会的責任”と見なされるようになっています。
厚生労働省の令和5年度「都道府県労働局雇用均等室に寄せられたセクハラ等の相談件数」は約7千件を超えています。
これは実際に相談に至った数であり,潜在的な被害はさらに多いと考えられています。
こうした現状を放置すれば,企業は次のようなリスクを負うことになります。
労働人口が減少する中,優秀な人材を確保するためには,単に給与や待遇だけでなく,「安心して働ける職場」であることが求められています。セクハラを放置している企業は,採用の段階で候補者から敬遠される可能性もあります。
一方で,適切な対策を講じている企業は,「ここなら安心して働けそう」という信頼や好感度を獲得することができます。
男女雇用機会均等法やパワハラ防止法など法的整備は進んでいますが,単に法律に従うだけでは,信頼される企業とは言えない時代です。
重要なのは,法令順守に加え「企業の姿勢」として,
企業がこのような動きを積極的に行うことが重要になるでしょう。

職場でセクハラが発生した場合,企業には重大な法的責任と社会的責任が問われます。
「加害者と被害者の個人間の問題」として片付けることはすでに許されない時代です。
企業の責任は主に以下の法律に基づいて発生します。
企業には,職場におけるセクハラを防止し,適切に対応する義務があります。
具体的には,被害の申し出があった場合の対応体制の整備や,再発防止の措置を講じる必要があります。
使用者(企業)は,労働者が安全かつ健康に働けるよう,職場環境を整える義務があります。
セクハラを放置することは,この義務に反する行為と見なされる可能性があります。
社員が職務中に第三者(同僚など)に損害を与えた場合,その社員を雇っている企業(使用者)も損害賠償責任を負うことがあります。
男女雇用機会均等法や労働契約法,民法上の使用者責任など,企業には明確な義務が課されています。
「知らなかった」「対応が遅れた」では,企業としての信頼を大きく損なってしまいます。
セクハラが疑われる事案が発生した際,企業には迅速かつ適切な初動対応が求められます。対応が遅れたり不適切であったりすると,被害が深刻化するだけでなく,企業そのものの責任も問われる可能性があります。
以下は、企業として取るべき初動対応の基本的な流れとポイントです。
被害者が安心して話せる環境づくりが事実確認の第一歩となります。
注意点は, 一方の言い分だけで判断せず,公平中立な立場で状況を把握します。
客観性と信頼性の高い対応が,後のトラブル防止につながります。
被害者側に不利益とならないよう,本人の意向を尊重することが大切です。
曖昧な処分は再発のリスクを高めます。毅然とした対応が必要です。
セクハラ対応はスピードと信頼性が命です。
「企業としてどう向き合うか」が問われる初動対応こそ,社員にとって「安心して働ける会社かどうか」を判断するポイントになります。

セクハラは「発生してからの対応」だけでなく,「未然に防ぐ仕組みづくり」が何よりも重要です。

セクハラ問題は,一度でも発生すれば企業の信用を大きく損なうリスクがあります。
だからこそ,予防・初動対応・再発防止までを一貫して設計することが不可欠です。
社内ルールの見直しや研修の充実は,明日からでも始められる取り組みです。
経営層も管理職も,社員一人ひとりの安心・安全な職場づくりのために,本気で向き合う必要があります。
セクハラを防止し,信頼される組織を目指すために,企業は今できることから一歩ずつ取り組んでいきましょう。

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。