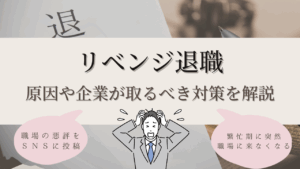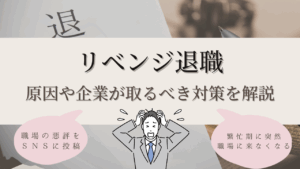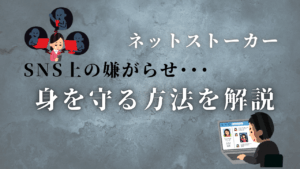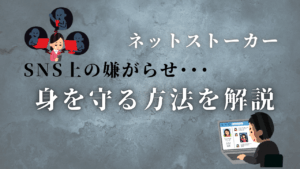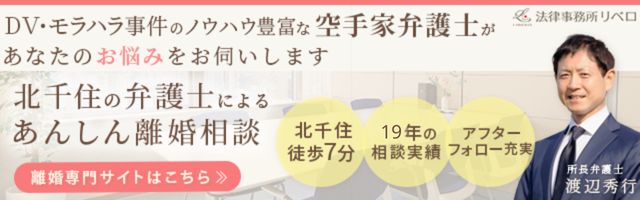
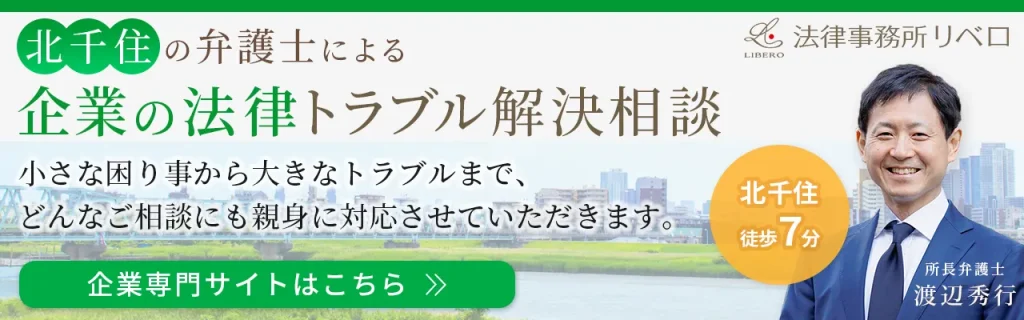
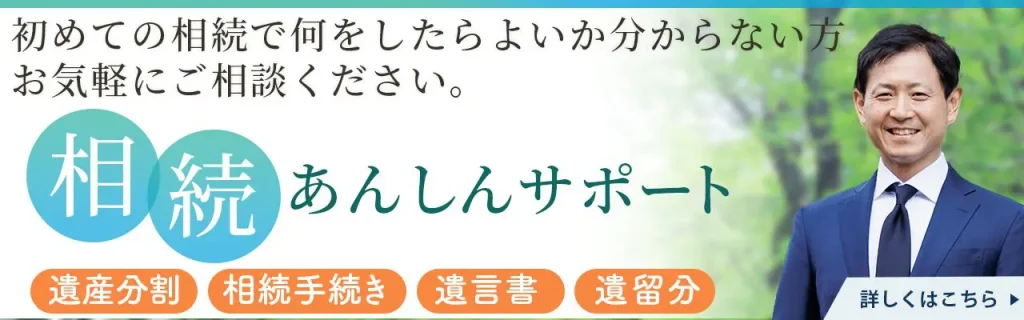


法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
当事者間で話がまとまらない場合には裁判所で話し合い(調停)の場をもうけたり、訴訟手続きを通じて解決する方法があります。
話し合いは一般的に労働審判制度と呼ばれ、労働者と使用者の間の労働関係について裁判官1名と労使の専門家2名で構成する委員会(労働審判委員会)が3回以内の期日で審理し、調停による解決を試み、調停が成立しない場合には審判を行う制度を指します。
一方労働訴訟は、一般的な裁判と同様に裁判所に訴訟を申し立て、裁判期日に双方の言い分を裁判官につたえ、紛争解決の方法を仰ぎます。
労働審判は、第1回期日に労働審判委員会が主張と争点の整理を終えなければならないので、申立を受けた使用者は、第1回期日の前に原則として主張を記載した答弁書と証拠を全て提出しなければなりません。
しかも、申立てから40日以内に第1回期日が指定され、その1週間前までに反論の提出を求められるので、主張(反論)証拠を提出するまでに30日程度しか余裕がありません。
従って、労働審判の申立書が届いたら直ちに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
答弁書には、証拠で提出した陳述書の内容も記載し、主張(反論)が具体的な証拠に裏付けられていることも示す必要があります。
第3回期日に、審判が口頭で告知されます。審判に対し、当事者は2週間以内に裁判所に異議を申し立てれば、労働審判はその効力を失い、申立時に遡って、地方裁判所に訴え提起があったものとみなされます。
労働審判を起こされたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。
原告と被告との間において主張(言い分)が相互になされ、それに伴い必要な書証の調べがなされ、その後証人尋問がなされます。それと並行するか、証人尋問の後辺りに和解の話合いが裁判所を介してなされるのが一般です。
会社の対応としては、勝てる十分な見込みがあるなら判決を求めるのがよいと思われますが、それ以外の場合は、和解に応じるかあくまで判決を求めるかのいずれかになります。
和解に応じるにしても、会社の信用が失墜しないような和解を工夫する必要があります。
なお、判決で会社側が敗訴すると、控訴しても被控訴人(元従業員)は強気になり、1審より会社に有利な和解をするのは難しくなりがちですから、勝訴の確信がない限り判決を求めるか否かについて慎重な判断が求められます。
労働訴訟において下記のようなポイントが争点になりがちです。
解雇を例に挙げてご紹介します。
懲戒処分が有効となるには
が必要となり、これらが主として争われます。
使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金の支払いをしなければなりません。
これがなされているかが争点となる場合があります。また、解雇は社会通念上相当でなければなりませんので、それが問題となります。
整理解雇が有効となるには
が検討要素となります。
 弁護士 渡辺
弁護士 渡辺労働訴訟の典型的なものに従業員地位確認請求事件があります。
これは従業員が雇用主から解雇された場合、解雇が無効で従業員の地位が存在することを確認し、給与の支払い等を求める訴えのことです。
このような訴訟を起こされた場合は、どう対応すべきか、弁護士にご相談されることをお勧めします。


特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。


弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。