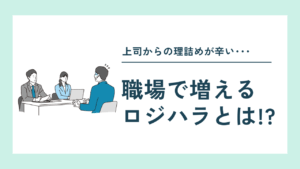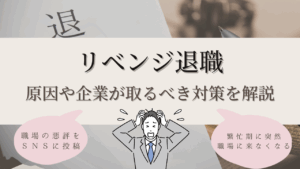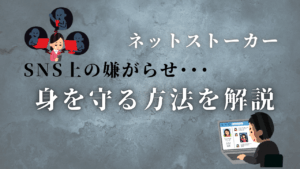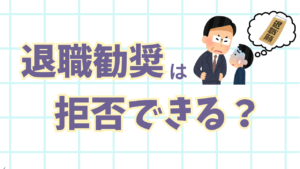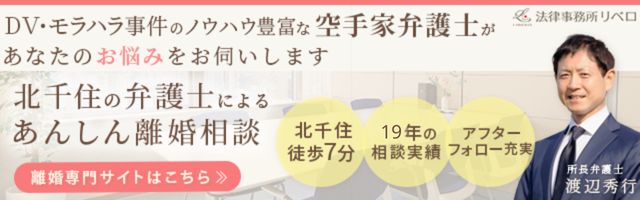
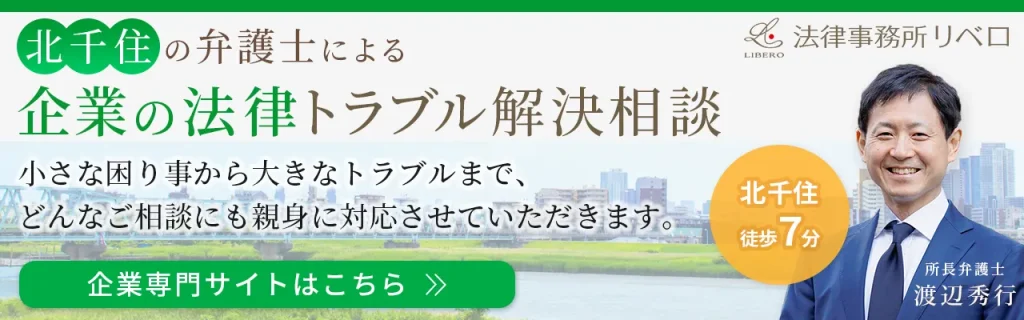
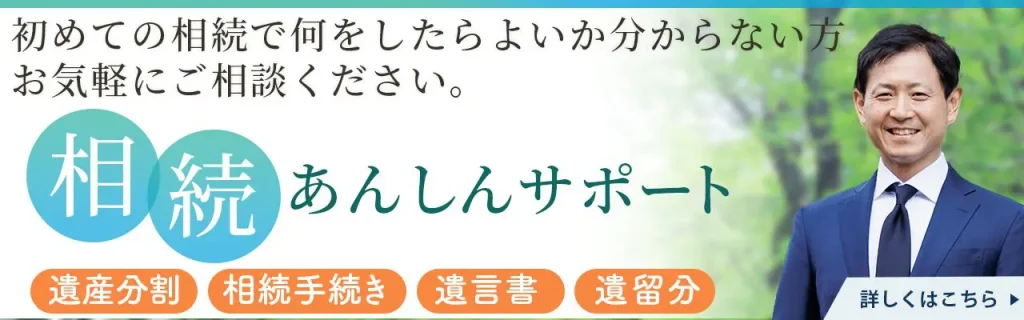
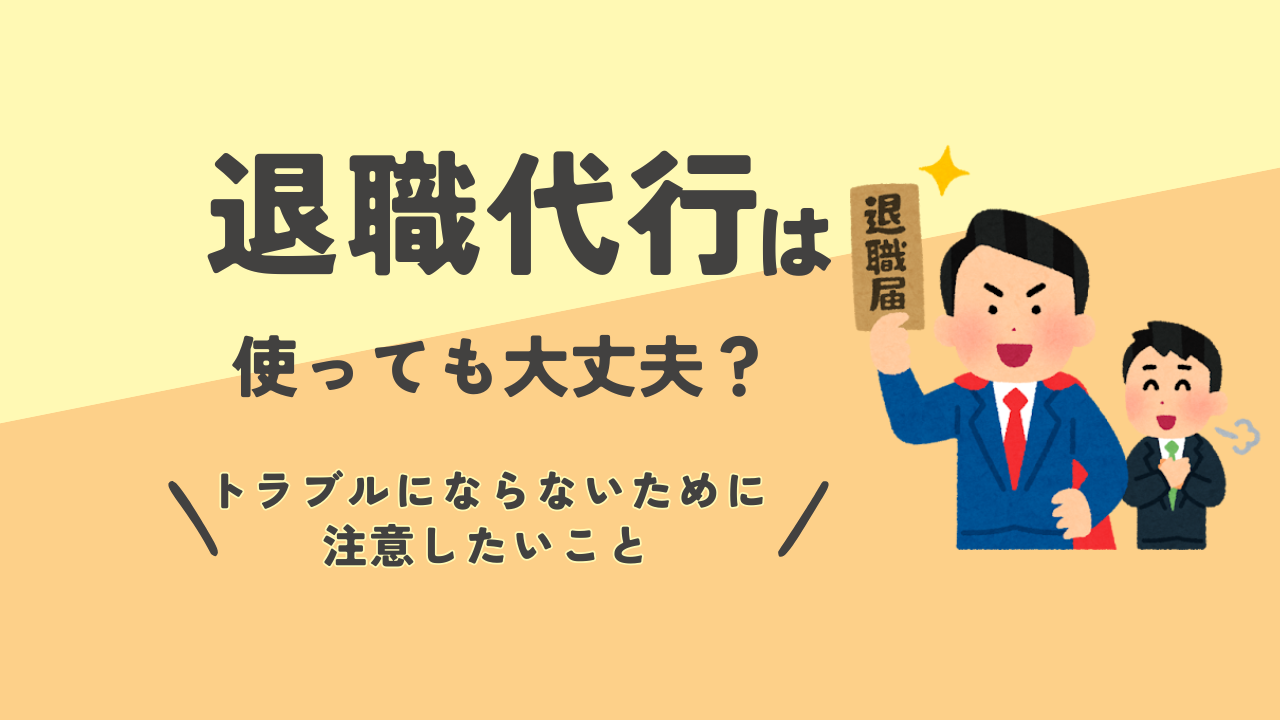

法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
「会社を辞めたいけど、上司に言い辛い」
「このまえ辞める意思を伝えたのに引き留められてしまって退職できない…」
そんな悩みを抱える人が増える中、“退職代行サービス”がいま注目を集めています。
電話1本またはメールで退職の手続きを代行してくれる手軽さから、利用者が急増しており,特に20〜30代の人の利用が多いです。
でも、その一方で
「退職代行を使ったら訴えられるって聞いたけど、本当?」
「会社から自分に連絡が来たらどうすればいいの?」
「トラブルになったら責任はとってくれるの?」
といった不安の声も後を絶ちません。
実は、退職代行の使い方を間違えると、法的トラブルに発展するリスクもゼロではありません。
この記事では、弁護士の視点から退職代行の法的リスクや,安全に使うためのポイントをわかりやすく解説します。

退職代行とは、本人に代わって会社に「退職の意思」を伝えてくれるサービスのことです。
依頼を受けた退職代行業者が、電話やメールなどで会社に連絡を入れ、「○○さんは退職の意思を固めています」と伝えてくれるので、本人はもう直接会社とやりとりしなくてもよいところが特徴です。
特に、「人手不足で退職したいと言いづらい環境にある」「退職の意思を伝えると引き留められてしまった」などといった理由で利用されることが多いです。
退職代行には,弁護士に依頼して企業と退職交渉をおこなうものと,利用者の退職意思を企業に代わりに伝えてくれる民間型の2種類があります。
| 種類 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 弁護士型 | 弁護士が対応する | 会社との交渉(有給・残業代請求)などの法律行為ができる。 料金がやや高額。 |
| 民間型(非弁) | 一般企業が運営・対応する | 退職の意思を代わりに伝えてくれる。 手軽で費用も安いが,会社へ交渉することやトラブルになった場合は対応ができない。 |
最近の若い世代は、辞める=他の人に迷惑をかけてしまうという発想よりも、自分の心身を守ることを優先する考え方が広がっています。
SNS上でも「退職代行でスッキリ辞めることができた!」「もう出社しなくてよくなった!」といった体験談が注目されるなど、“辞め方”の価値観が変わりつつあるのも理由の一つです。
また、ブラック企業やパワハラの問題が表面化し、“まともに辞めさせてくれない職場”が珍しくない現代では、退職代行が“最後の砦”として頼られている側面もあります。

退職代行を使うと、「会社に迷惑をかけた」として損害賠償を請求されるのではないか?と心配する人も多いです。
中には「代行を使って辞めたら名誉毀損になると聞いた」といった噂もあるようです。
しかし、結論から言うと普通の使い方をしていれば、訴えられるリスクはほとんどありません。
というのも、日本の労働法では、労働者には「退職の自由」が認められているからです。
民法627条では、2週間前に退職の意思を伝えれば辞めることができるとされており、本人が直接伝えなくても“第三者を通じて意思を示す”ことは合法です。
退職代行を使って仕事を辞めることは自体は違法ではないと述べましたが,企業と利用者の間でトラブルに発展するケースも珍しくありません。
例えば,民間の退職代行業者を使ったが,残っている有給休暇を消化できずに退職に至ってしまったり
代行をつかって退職の意思を伝えてもらったのに,企業から利用者本人へ直接連絡がくるケースなどがあります。
また、あたかも交渉までしてくれるような宣伝をしている退職代行業者も存在します。
しかし法律上、弁護士以外は「退職交渉(有給・未払い残業代の請求など)」を行うことができません。
民間業者を利用した場合、トラブルが起きた時に法的な対応ができない=最終的に自分がリスクを背負うことにもなりかねませんので利用の際は注意しましょう。

まず気をつけたいのが、「会社の就業規則」や「引き継ぎ」の扱いです。
確かに法律上は、退職の意思を伝えてから2週間で辞められるとされていますが、
就業規則で「1ヶ月前に申告」と定められている会社もあります。
とはいえ、就業規則が絶対というわけではなく、法的には2週間前に通知すれば問題が無いというのが原則です。
ただし、引き継ぎを放棄して突然辞めたり、業務を完全に放り出すような辞め方をすれば、
「業務に損害を与えた」とみなされるリスクもゼロではありません。
退職代行を使うことを決めた際には、可能な限り引き継ぎメモを残すなど、
最低限の誠意は見せておくとトラブルになりにくいです。
「急に辞めたら損害賠償請求をされるかも…」という不安を抱える人も多いですが、
民間の労働者が“普通に退職しただけ”で損害賠償が認められるケースはほぼありません。
ただし、以下のような場合は要注意です:
こうしたケースでは、退職そのものではなく、“結果的な損害”に対する請求が発生する可能性があります。
つまり、「退職代行を使ったから訴えられる」のではなく、
辞め方や契約内容に問題があった場合に限って、法的リスクが発生します。
トラブルを避けたいということであれば,弁護士が運営する退職代行サービスを使うのが安心です。
費用は民間代行業者よりも高額ですが、その分リスク管理がしっかりしていて安心して退職できることが最大のメリットです。

退職代行は精神的に限界なときや、どうしても会社に言い出せない状況を打開する強力な手段です。
実際、退職代行を利用して救われた人もたくさんいます。
とはいえ「訴えられたり会社とトラブルになるかも…」という不安があるのも当然のこと。
でも安心してください。
この記事でお伝えしたように、退職代行を“正しく使えば”、法的に問題となるケースはごくまれです。
安心して退職代行を使うためには
つまり、退職代行を“使うこと”自体が問題なのではなく“どう使うか”が重要ということです。
会社を辞めることは、決して悪いことではありません。
むしろ、自分の人生を守るために必要な選択肢のひとつです。
不安に流されず、正しい知識と準備で、スムーズな退職を実現しましょう。

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。