
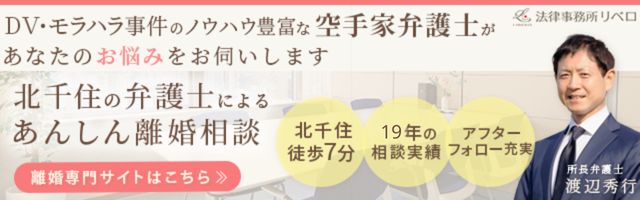
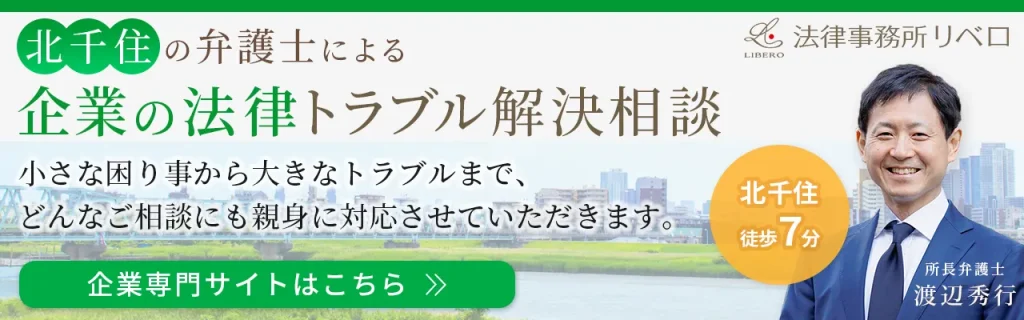
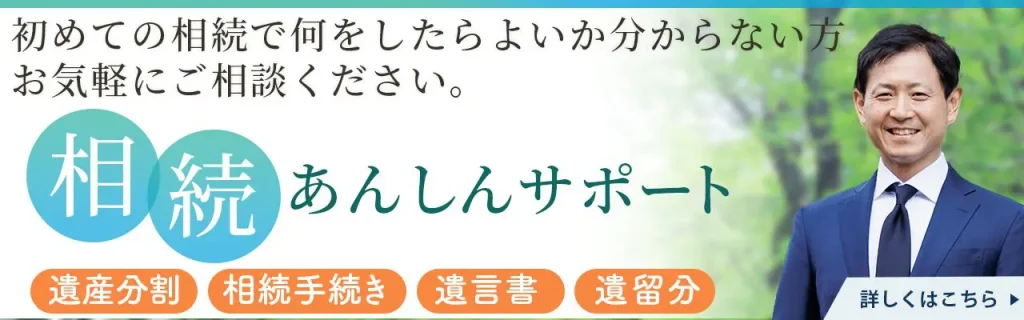


出願の内容を記載した公報が自由に閲覧可能になります。
この出願公開は、出願の取下げがあったものを除き、原則としてすべての特許出願が公開されます。
従来は、全ての特許出願を審査した後、その出願内容を公表していましたが、出願件数が増大し、審査時間に時間がかかるようになると、同じ技術を重複して研究し、重複した出願がなされることが多くなってきました。
そこで、早い段階で出願内容が公開し、このような弊害を防止するようにしたのです。
ところで、出願公開されると、発明の内容が公開されるので、模倣される可能性が高まります。そこで、出願人を保護するため、補償金請求権(※)が認められています。
※補償金請求権・・・出願人が出願公開された特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をした後、特許権の設定登録までの間に、業として、その発明の実施をした者に対し、その発明が特許されていたとした場合に実施料相当額の補償金の支払いを請求できる権利。
特許出願された発明が、特許として登録されるかどうかは、特許庁の審査官による実体審査で判断されます。この実体審査は全ての特許出願に対して行われるのではなく、出願審査の請求があった出願だけが審査されます。
以下のような場合には、審査請求されないことが多いです。
出願審査を請求するためには、
1出願につき、138,000円+(請求項の数×4,000円)の費用が必要です。
審査官が、拒絶理由を発見した場合(進歩性がない等)、そのまま拒絶査定をするわけではなく、まずは、出願人に拒絶の理由を通知し(拒絶理由通知書が送られます)、それに対する出願人の意見を聞きます。
この段階で、出願人としては、従来技術との違いを述べた意見書を提出したり、違いを明確化するために、特許請求の内容等を修正する補正書を提出することが出来ます。
意見書、補正書等で、拒絶理由が解消された場合、特許査定が下されます。
一方、拒絶理由が解消されていない場合、拒絶査定が下されます。
なお、実務上、拒絶理由の多くは、新規性、進歩性の欠如か、明細書の記載が明瞭でないとする記載不備に関するものです。
審査官が、拒絶理由を発見しなかった場合や、拒絶理由が解消した場合には特許査定が下されます。
特許査定後、30日以内に、1年目~3年目までの特許料の納付すると、特許登録されます。
特許登録後、特許権が発生致します。
特許権が発生すると、特許公報(特許掲載公報)に特許の内容が掲載されます。
なお、特許料は、以下のとおりで、年毎に高くなっていきますので、特許の価値等を踏まえた上で、登録し続けるか判断する必要があります。
特許料
特許権の存続期間は、出願から最長20年です。
なお、一部の技術分野(医薬品等)では、他の法律による許認可等が必要とされ、許認可が下りるまで、時間がかかるため、存続期間の延長の制度が設けられております(最長年まで)。
拒絶理由が解消しない場合、拒絶査定が下されます。
拒絶査定に不服がある場合、
拒絶査定不服審判→審決取消訴訟→上告
という方法で、争うことになります。