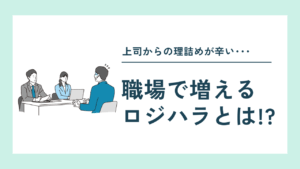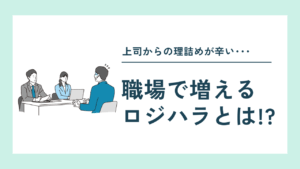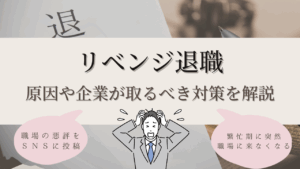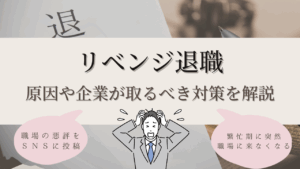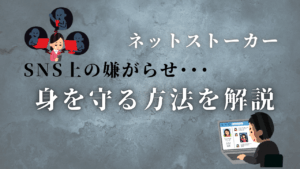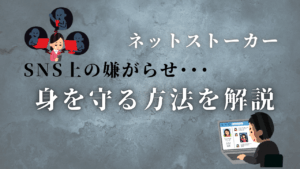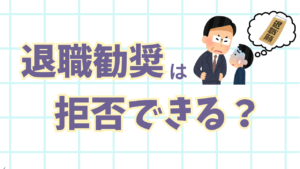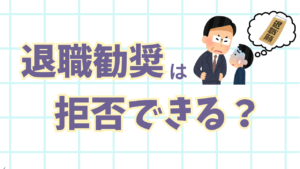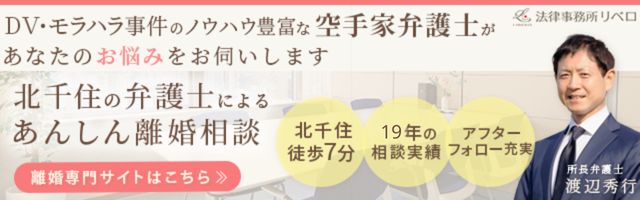
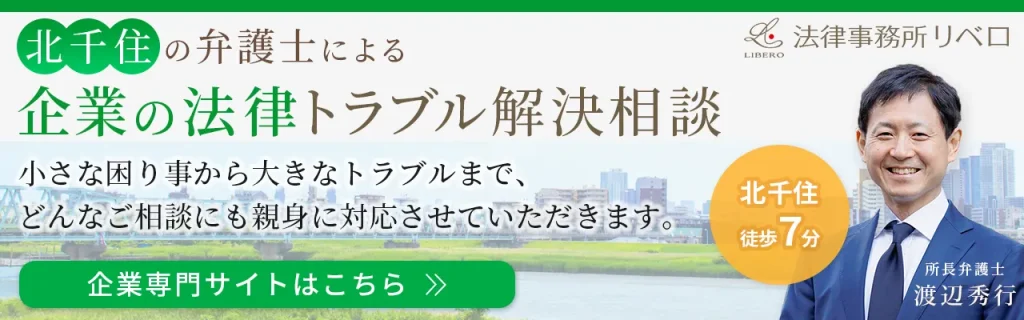
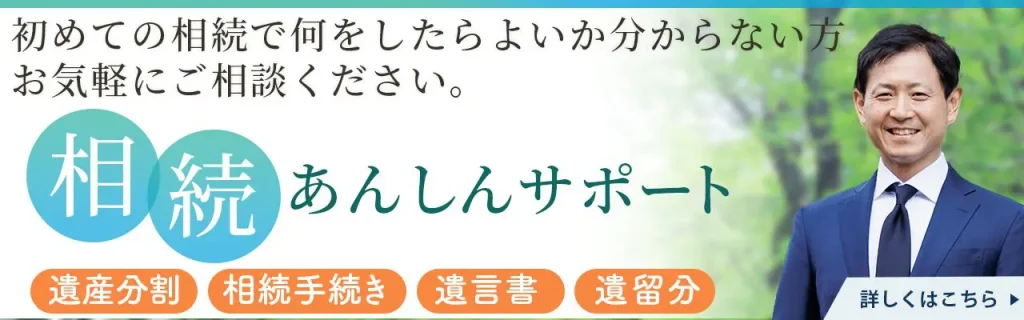
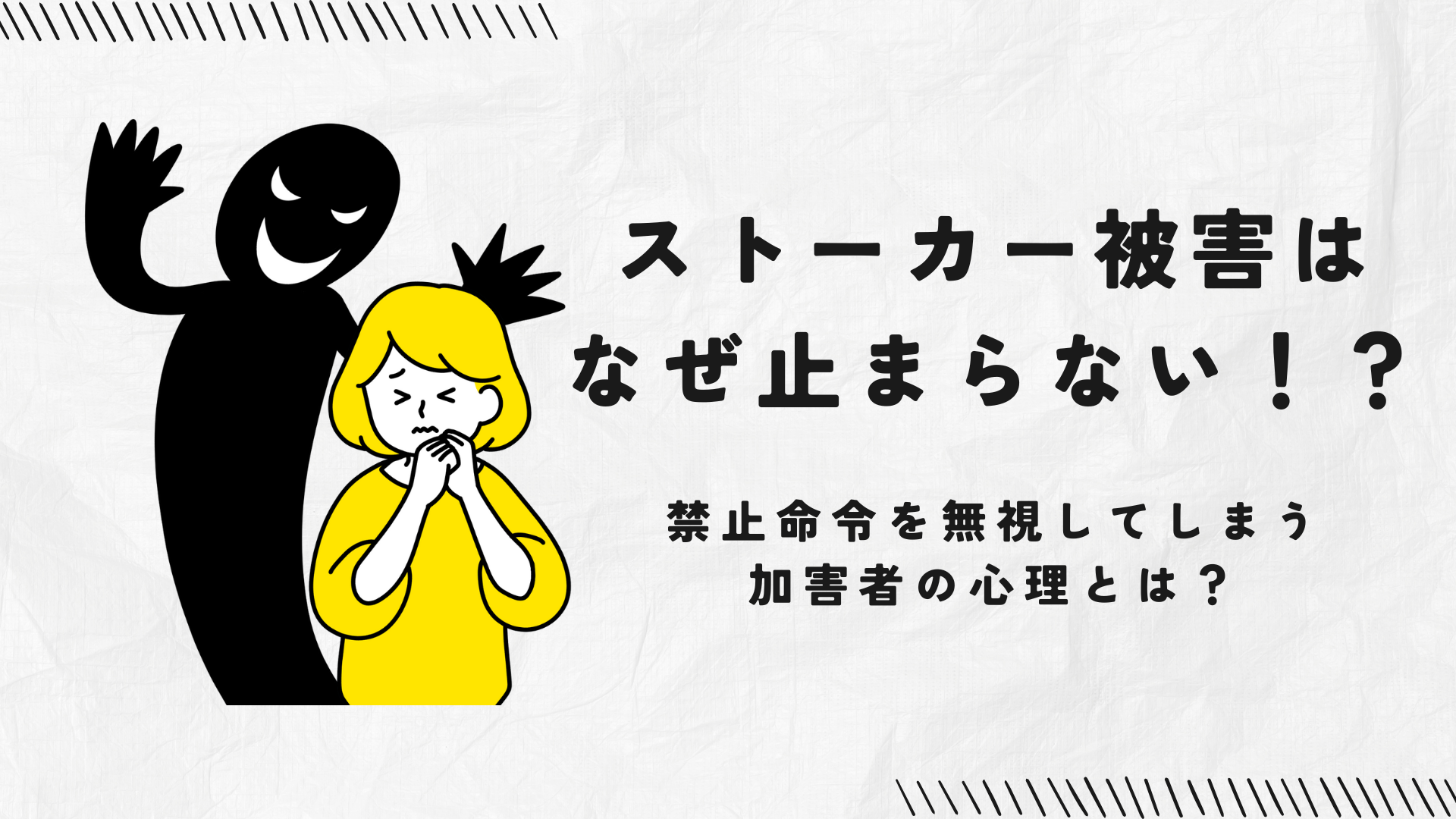

法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
2025年5月、神奈川県川崎市で、若い女性が元交際相手とみられる男から命を奪われるという事件が報じられました。
こちらの事件は、被害女性が以前から元交際相手からのストーカー被害を警察に何度も相談していたにもかかわらず、「事件性がない」と判断され、実質的な対応はされなかったと報道されています。
また2024年5月には新宿区で女性が、自宅マンション前で刺殺されるという事件もありました。加害者とされる男性は、かつて被害女性に対するストーカー行為で逮捕され、1年間の接近禁止命令が出されていた人物です。しかし、禁止命令の効力が切れた後、女性を待ち伏せし、凶行に及びました。
どちらの事件も、女性がストーカー被害を警察に相談していたにもかかわらず、事件を未然に防げなかったという共通点があります。
なぜこのような事件が繰り返されてしまうのでしょうか?

ストーカー被害が社会問題化する中、国が法整備を進めた結果、2000年11月に施行されたのがストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)です。
この法律は、つきまといや待ち伏せ・無言電話・SNSでの執拗なメッセージの送信など、特定の人物に対する執着的な行為をストーカー行為として明確に定義し、警察が警告や命令を出せるようにしたものです。
その中でも、加害者に対して出される最も強い措置が禁止命令です。
これは、ストーカー行為の継続・再発を防ぐためのもので,法的拘束力があります。
違反すれば刑事罰の対象となるため、一定の抑止力を持っています。
禁止命令には主に以下の内容が含まれます
禁止命令の有効期間は1年間であり,期間が終了する時点でも危険な状況にある場合にはさらに1年更新することができます。

近年増えているのが,善意や偶然を装い、被害者に警戒心を持たせない形で行われるストーカー行為です。
典型的な例としては,実在する企業やサービスを装い被害者の自宅や職場に「景品」「サンプル品」「プレゼント」などを送りつけるケースです。
一見すると単なる販促や誤配送のように見えますが,荷物の中に盗聴器や小型の発信機が仕込まれていたという事例も報告されています。
被害者自身が開封してしまうことで,室内の会話や生活音が外部に漏れてしまう恐れがあります。
また被害者の隙をつき,ワイヤレスイヤホンやAirtag等の小型端末をカバンのなかに勝手にいれ,GPS機能を利用して行動を追跡するといった手口も確認されています。
こうした行為の厄介な点は
という理由から,被害として認識されにくいことにあります。
しかし,本人の意思に反して位置情報を把握したり,私生活を監視したりする行為は,状況によってはストーカー規制法やプライバシーの侵害に該当する可能性があります。
少しでも違和感を覚えた場合は,早い段階で記録を残し,警察や専門家に相談することが重要です。

ストーカー行為に対しては、ストーカー規制法や禁止命令といった法的手段が整備されていることを説明しました。
しかし、近年の事件が示すように、法律だけではストーカー被害を完全に防ぐことはできません。その理由の一つが、加害者の内面に潜む「執着心」の存在です。
ストーカー行為と聞くと、「元恋人が復縁を迫ってくる」といった恋愛絡みの問題を思い浮かべがちですが、実際にはそう単純な構図ではありません。
ストーカーの中には、「自分の支配下に置きたい」「自分を拒否した相手を許せない」という歪んだ執着心や支配・欲求に突き動かされているケースが多くあります。
このような心理状態の加害者は、たとえ警察に通報されても、禁止命令を受けても、「それでも会いに行きたい」「命を奪ってでも思い知らせたい」と行動に出ることがあり、理屈やルールが通用しない相手となってしまいます。
冒頭で触れた2024年5月に起こった事件では、命令の効力が切れたタイミングを狙って加害者が待ち伏せし、凶行に及びました。これは「禁止命令を出していたからもう大丈夫」と思っていた被害者側の“安心”が、裏切られたケースとも言えます。
このようにストーカー加害者の中には、命令の期限が切れるのを待って再び接近してくるような者もいるため,禁止命令が出たとしても以前と同じ生活圏で生活を続けたり,警戒を緩めることがないよう注意しましょう。
法律は、一定の抑止力や制裁をもたらすことができます。
しかし、加害者の執着に対しては、継続的な警戒・支援・避難体制の整備が不可欠です。
たとえば禁止命令の期間が終わった後でも,警察や支援機関が定期的に被害者へ状況確認をすることや、被害者の生活圏の変更やシェルター提供など根本的なリスク回避のための情報提供をし,社会全体で被害者を支援することが必要になります。

ストーカー被害に遭ったとき、多くの人がまず思い浮かべるのは「警察に相談すればなんとかしてくれる」という希望です。
ところが、実際の現場では「通報したのに動いてくれなかった」「事件が起きてからでないと対応しない」といった声が後を絶ちません。なぜこのようなズレが生じるのでしょうか。
ストーカー規制法に基づく警告や禁止命令を出すためには、警察が「ストーカー行為が確認できる」ことを前提としています。
つまり、加害者の行動を明確に記録・証明できなければ、警察は強く動けないという制約があるのです。
たとえば、SNSでのメッセージや、無言電話、GPSによる追跡など、見えにくい・証拠が残りにくい行為では、被害者の不安が伝わっても「違法とは言い切れない」と判断されることがあります。
また,警察は民事不介入の原則に従っており、形式的な相談だけでは強制的な介入はできません。
しかし、多くの被害者は「逆に相手を刺激してしまうのでは・・・」といった不安から、被害届を出すことに躊躇します。
このため、警察側も積極的に動けず、加害者には「まだ大丈夫」という誤った安心感を与えてしまうという悪循環が生まれているのが現実です。
さらに問題なのは、ストーカー被害への対応が警察署や担当者によって大きくばらつきがある点です。
ストーカー事案に精通した担当者がいる地域では迅速な警告や禁止命令が行われる一方で、経験の浅い担当者が対応すると「とりあえず様子を見ましょう」で終わることもあります。
実際には、“命の危険があるかもしれない”段階で初めて警察が本格的に動くこともあり、それでは遅すぎるケースも珍しくありません。
 弁護士 渡辺
弁護士 渡辺警察に相談してもなかなか動いてもらえなかった場合には,弁護士に相談し書面で警察へ対応を求める方法もあります。


ストーカー行為への法的対処には限界がある以上、被害者自身が身を守るために現実的かつ多角的な対策を講じる必要があります。
ストーカー被害が疑われる段階から実行できる、実効性のある自己防衛策は以下の通りです。
警察や第三者期間に相談に行く際に質問される事項をまとめました。
以下の内容をメモ等にまとめておくとスムーズに相談出来ると思います。


| 名称 | ダイヤル | 詳細 |
|---|---|---|
| 警察 | 110番または#9110 | まずは警察へ相談しましょう。とりあえず相談したいという方は#9110、緊急性がありすぐに対応が必要な場合は110番へ連絡しましょう。 |
| 女性相談支援センター | #8778 | 各都道府県に設置されている公的機関です。困難な問題を抱える女性に寄り添って包括的支援を行っています。 |
| 女性の人権ホットライン | 0570-070-810 | 女性に関する人権相談を電話で受け付けています。 インターネットからでも相談可能です。 |
| 法テラス | 0120-079714 (犯罪被害者支援ダイヤル) | 国が設置した法律トラブル解決機関です。犯罪被害に遭った方には,被害者支援に理解のある弁護士の紹介等も行っています。 |


ストーカー行為は単なる恋愛のもつれではなく、重大な人権侵害かつ命の危険を伴う犯罪です。
ストーカー規制法や禁止命令といった法的制度は整備されつつあるものの、それだけで完全に被害を防ぐことは難しいのが現実です。
警察は「証拠がない」「事件性が低い」と判断すると、動きが遅れることがあります。禁止命令が出ていても、それを破る加害者は後を絶たず、制度の限界を突いてくるケースもあります。
被害を繰り返さないためには、一時的な対処ではなく、長期的な視点での安全確保が重要です。
“また起きてしまった”を、次こそ繰り返さないために,私たち一人ひとりが、ストーカー問題の本質と向き合う必要があります。


特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。


弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。