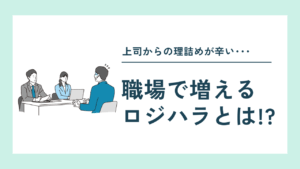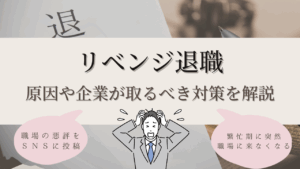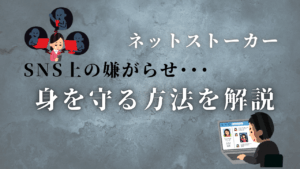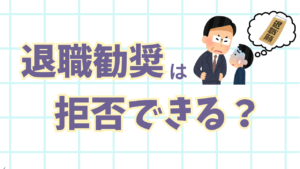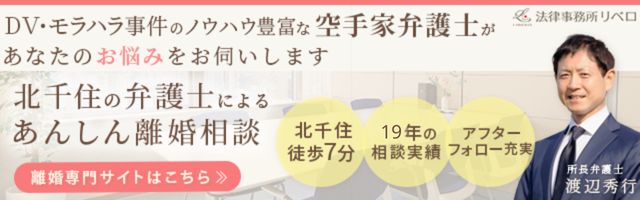
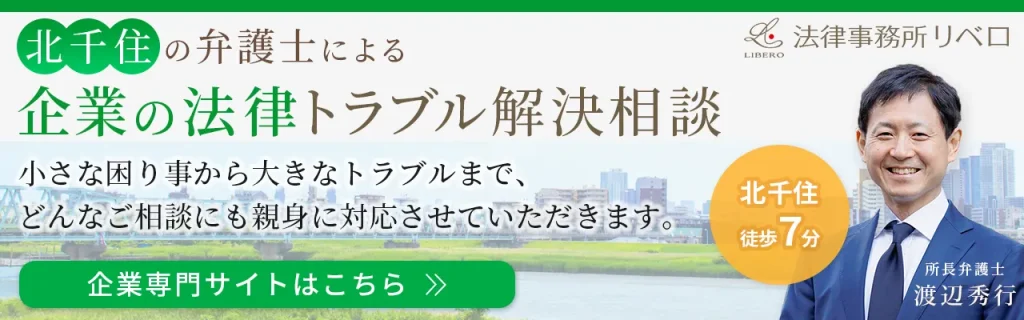
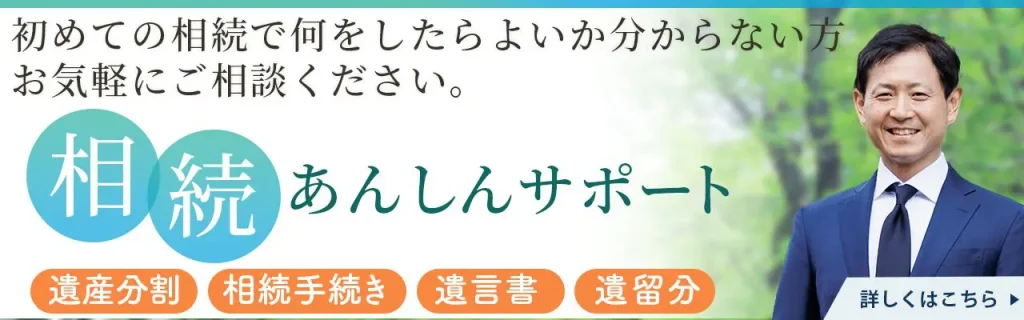


法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
退職を申し出たのに、「今辞められたら困る」と会社から引き止められたり、「損害賠償請求するぞ」と脅されたり…。
近年、こうした企業による“退職ブロック”の問題が急増しています。
特に人手不足の業界やいわゆるブラック企業では、法的根拠のない強引な引き止めが横行しており、精神的な負担から辞めることすら諦めてしまう人も少なくありません。
しかし日本の法律では「退職の自由」が保障されており、会社の許可がなくても、一定の手続きを踏めば誰でも退職することができます。
この記事では、退職を拒否・引き止めされた場合にとるべき正しい対応方法や、違法な引き止めの具体例、法的に有効な退職手続きの進め方について、わかりやすく解説します。
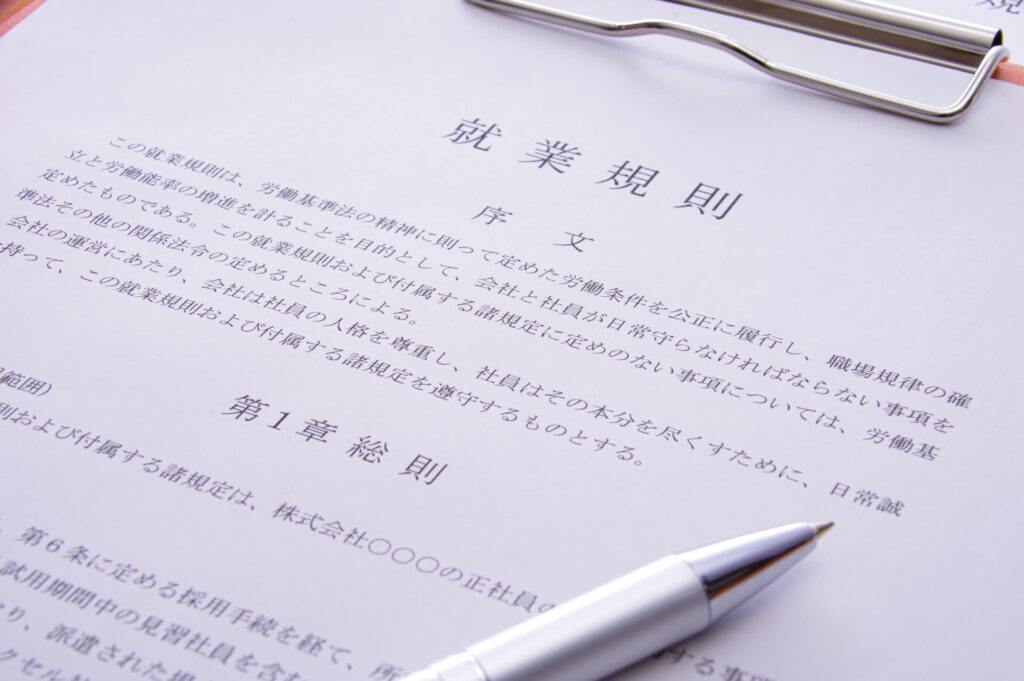
「上司が退職を認めてくれない」「退職届を受け取ってもらえない」といった声をよく耳にしますが、そもそも退職に“会社の許可”は必要なのでしょうか?
答えは不要です。
日本の民法では、労働者には退職の自由が認められており、使用者(会社)の承諾がなくても、一定のルールを守れば退職は成立します。
たとえば、正社員などの期間の定めがない契約で働いている場合は、民法627条により「原則として2週間前に退職の意思を伝えれば辞められる」とされています。
つまり、会社がなんといおうと、退職の意思を伝えてから2週間経過すれば、法的には労働契約を終了できるのです。
就業規則に「退職をする場合は1ヶ月前に申し出ること」と書かれていても、それが絶対ではありません。
退職はあくまで“労働者の権利”です。会社の都合で引き延ばされたり、拒否されたりしても、法律上は効力があるという点をしっかり押さえておきましょう。
「正社員じゃないから、簡単には辞められないのでは?」と不安になる方も多いですが、結論から言うと、アルバイトや契約社員、試用期間中の従業員でも、原則として退職は可能です。
まず、アルバイト(パート)など、期間の定めがない雇用契約の場合は、民法627条に基づき、2週間前に退職の意思を伝えれば辞めることができます。
これは正社員とまったく同じ扱いです。
一方、契約社員などの期間付き雇用の場合でも、やむを得ない事情(パワハラや長時間労働など)がある場合には中途退職が認められるケースもあります。
自己都合で辞める際は、就業規則や契約書の内容を確認しつつ、事前にしっかりと準備をしておくのがベストです。
試用期間中の退職も、基本的には上記と同じ考え方です。試用期間中であっても、労働契約は発生しているため、正当な手続きをとれば退職はできます。
つまり、どの雇用形態であっても、あなたには「辞める権利」があります。
自分の立場に関係なく、安心して退職の意思を伝えてかまいません。

退職の意思を伝えたにもかかわらず、会社側から強引な引き止めや脅しを受けるケースは少なくありません。
なかには、法的に問題のある対応も多く、放置していると精神的な負担や不利益が生じることもあります。
ここでは、実際によくある「違法の可能性がある退職妨害」の具体例を紹介します。
「お前が辞めたら会社が損害を被るぞ」「今辞めるなら損害賠償を請求する」などと脅されるケースがあります。
しかし、労働者が正当な手続きで退職することに対し、会社が損害賠償を請求するのは原則として認められていません。
特に、威圧的な言動で退職を思いとどまらせようとするのは、不当な圧力とみなされる可能性があり、場合によってはパワハラや違法行為と判断されることもあります。
会社側が退職届の受け取りを拒否し、「認めないから退職できない」と言ってくることもありますが、これも法的には無効です。
民法では、労働者の一方的な意思表示により退職できるとされており、会社の“許可”は不要です。
仮に退職届を受け取ってもらえなくても、内容証明郵便などで退職の意思を伝えれば法的効力が発生します。
退職の申し出後、「引き継ぎが終わるまでは辞められない」「有給は使えない」と言われることがあります。
しかし、有給休暇は労働者の正当な権利であり、退職前の有給消化を拒否することは原則としてできません。
また、後任が決まっていないことを理由に退職時期を引き延ばすのも、退職の自由を侵害する行為です。
業務引き継ぎの協力は大切ですが、それと退職を拒否することはまったく別問題です。
引き継ぎの有無に関係なく、労働契約は退職の意思表示から一定期間で終了します。
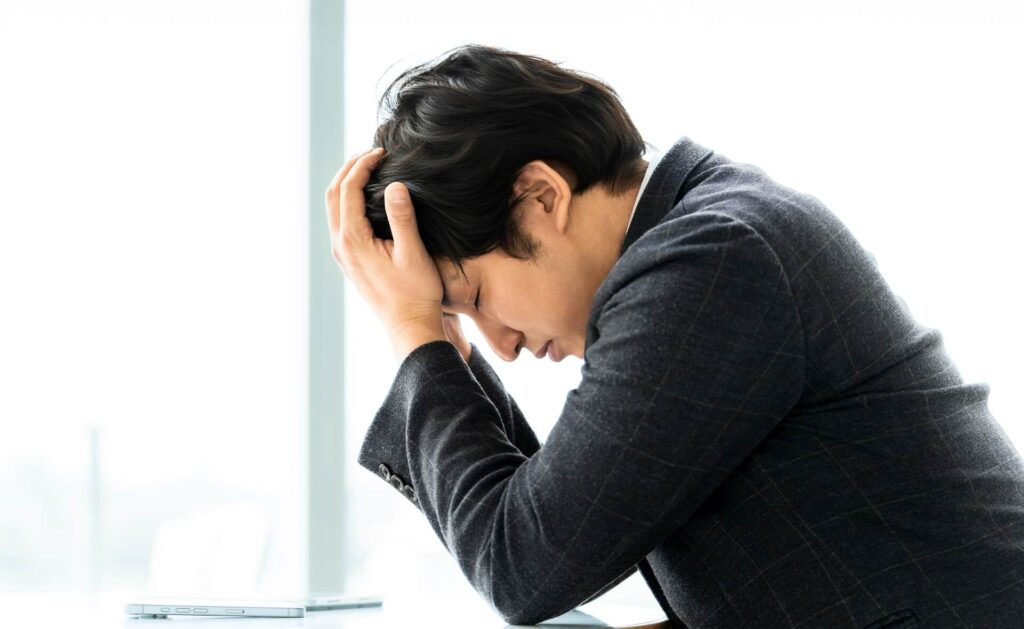
会社が退職を引き止めたり、退職届を受け取らなかったりしたとしても、適切な手続きを踏めば、法的にはきちんと退職することが可能です。ここでは、辞めさせてもらえない状況で労働者側が取るべき対応を3ステップで解説します。
まず重要なのが、「退職の意思表示をいつ、どのように伝えたか」です。退職は口頭でも法的には有効ですが、トラブル防止のためには書面(退職届・退職願)で提出するのが望ましいです。
上司に対して直接伝える場合も、あわせて紙の退職届やメールなど、証拠が残る手段で提出しましょう。「言った/言わない」の水掛け論になるのを防ぐことができます。
また、「退職届」は“辞めます”という確定の意思表示、「退職願」は“辞めたいです”というお願いなので、強い意志を示すなら「退職届」の方が適しています。
退職届を提出しても受け取りを拒否されたり、「保留にしてくれ」と言われたりすることもあります。その場合は、郵送による退職届の提出を検討しましょう。
とくに有効なのが内容証明郵便です。これは「誰が、誰に、いつ、どんな内容を送ったか」が記録に残る郵便のことで、証拠力が高く、法的効力を主張しやすくなります。
退職日は、内容証明の発送日から2週間後を記載しておくのが基本です(民法627条)。
届いた日から退職のカウントが始まるわけではないので、余裕を持って発送することが大切です。
会社側とのやりとりがトラブルになりそうな場合は、あらゆる証拠を残す意識が重要です。
後になって「そんな話はしていない」「届いていない」と言われても、第三者に見せられる証拠があれば主張を通しやすくなります。
弁護士や労基署に相談する際にも、有力な材料になります。

退職を認めず、脅したり、嫌がらせをしたりする会社の対応は、場合によっては違法行為(不法行為)として損害賠償請求の対象になることもあります。
退職を申し出たにもかかわらず、「損害賠償を請求する」「裏切り者だ」「辞めるなら仕事を干す」などと精神的な圧力をかけられた場合、名誉毀損やパワハラ、不法行為が成立する可能性があります。
こうした行為によってうつや不眠などの症状が出れば、精神的損害に対する慰謝料請求も可能です。
特に、暴言・脅迫・嫌がらせなどの具体的な言動が記録として残っている場合(録音・メッセージ・診断書など)は、証拠をもとに弁護士を通じて損害賠償請求や示談交渉ができるでしょう。
会社側の対応が明らかに不当だと感じたら、早めに外部機関へ相談することが大切です。
特に以下のような場合は、労働基準監督署に申告したり、弁護士に相談することで状況の打開が見込めます。
労基署には労働基準法違反に関する行政指導の権限があり、悪質な会社に対しては是正勧告や調査が行われることもあります。
一方、損害賠償や慰謝料など民事的な請求については、弁護士への相談が不可欠です。
勤務先からの引き止めに疲れてしまい直接退職の交渉ができないという場合には、退職代行サービスを利用するのも有効な手段です。
民間業者が退職の意思を会社に代わって伝えてくれるため、直接やり取りせずにスムーズに退職できるケースも増えています。
ただし、注意点もあります。
一般の退職代行業者は弁護士資格がないため、会社との交渉(賃金の未払い分請求や損害賠償など)はできません。これらの交渉も必要になる場合は、弁護士が運営する退職代行サービスを選ぶのと安心です。
利用を検討する際は、自分のケースが単純な退職意思の伝達で済むのか、それとも法的交渉が必要になるかを見極めて、適切な業者・弁護士に相談しましょう。
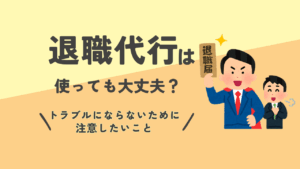

どれだけ強く引き止められたとしても、退職する権利はすべての労働者に平等に認められています。
退職を阻害しようとする会社の行為はあなたの権利を侵害する不当な行為かもしれません。
一時的な遠慮や恐怖心から、退職の意思をあいまいにしてしまうと、状況が長期化して心身に悪影響を及ぼすこともあります。
そんなときは一人で抱え込まず、労働基準監督署や弁護士、場合によっては退職代行など第三者に相談することが大切です。証拠を残しつつ、冷静に手続きを進めれば、たとえ会社側が認めなくても、法律上はきちんと退職が成立します。
自分の人生と健康を守るためにも、退職の自由をしっかり行使してください。

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。