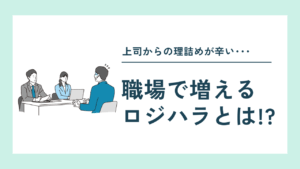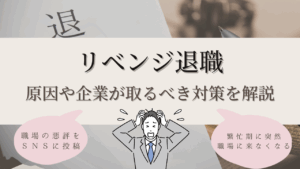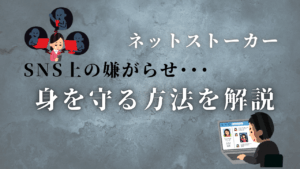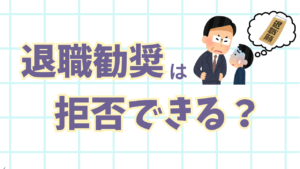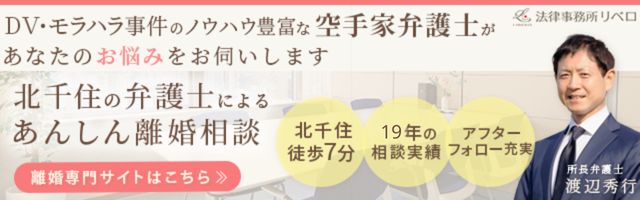
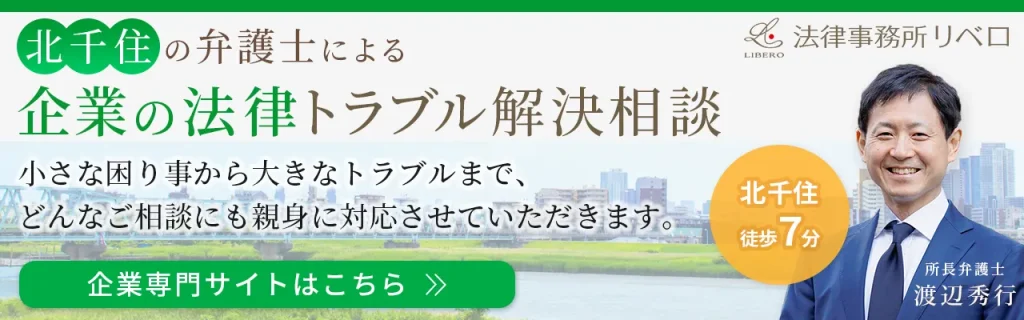
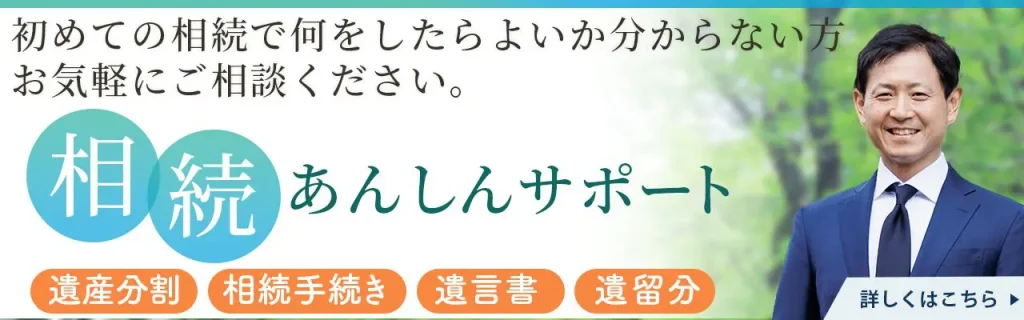
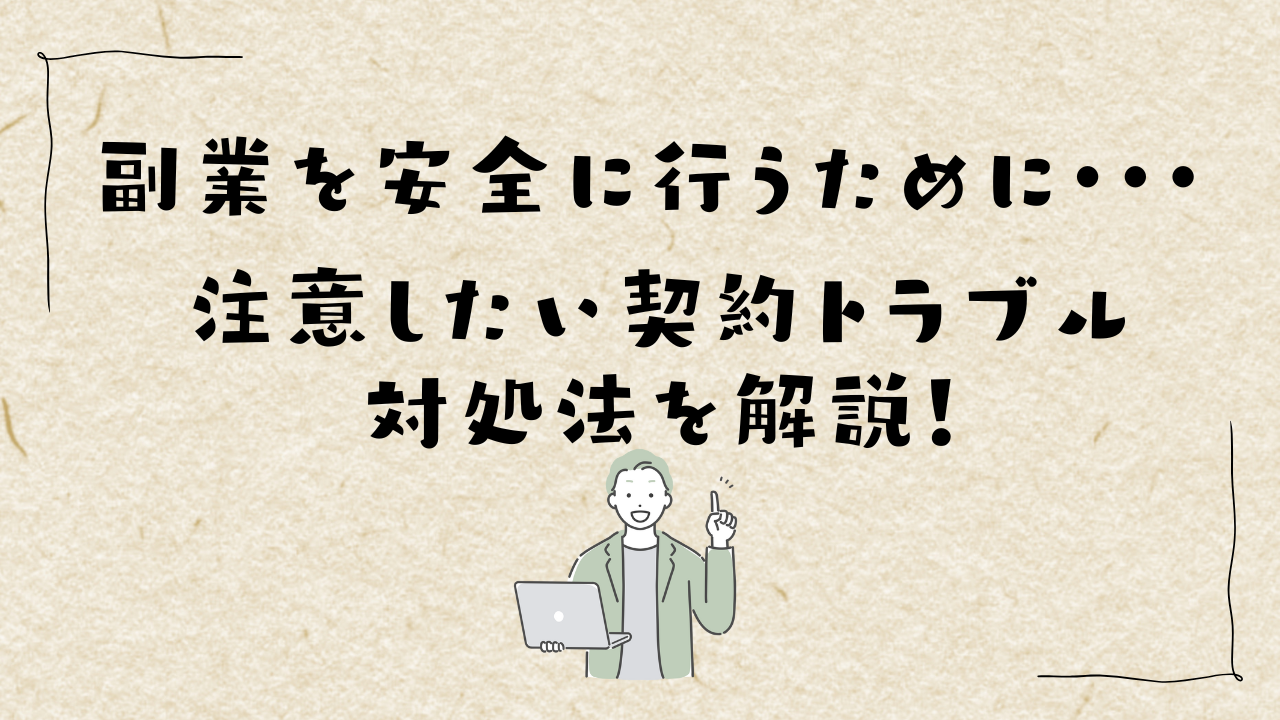

法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
副業が当たり前の時代になりました。
政府も副業や兼業を後押しする中、在宅ワークやフリーランスの形で副業に挑戦する人が年々増えています。
しかし、その裏で契約トラブルに巻き込まれるケースも急増していることをご存じでしょうか。
契約内容をよく確認せずに仕事を受けた結果、報酬を支払ってもらえなかったり、作成した成果物の権利をめぐって揉めたり……。
中には本業の会社と副業ルールを巡ってトラブルになる例もあります。
副業を安全に続けるためには、最低限押さえておくべき「契約リテラシー」が欠かせません。
この記事では、特にフリーランスとして副業をする中で,よくある契約トラブルの実例と、トラブルを防ぐためのポイントをわかりやすく解説します。

かつて日本では「副業禁止」が当たり前とされていました。
多くの企業が就業規則で副業を禁じ、ひとつの会社に長く勤めることが美徳とされていたためです。
しかし、近年の社会情勢の変化により、その考え方は大きく変わりつつあります。
政府は、少子高齢化による労働力不足や、経済の活性化を目的に、2018年に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定しました。
これにより企業に対して副業容認の方向へと舵を切るよう求めるようになりました。
さらに、終身雇用制度の限界、年金や老後資金への不安、そして個人がスキルアップやキャリア形成を図る必要性の高まりも、副業推進の追い風となっています。
最近では、リモートワークの普及やオンラインビジネスの拡大によって、場所や時間に縛られずに副業を始めることも容易になりました。
こうした背景から、副業は今や自己防衛の手段としても広く受け入れられつつあり、会社員が副収入を得るためだけでなく、将来に備える手段として副業に取り組む時代が到来しているのです。

副業にチャレンジする際、契約内容を軽視してしまうことで、さまざまなトラブルに巻き込まれるリスクがあります。
ここでは特に注意すべき典型的な例を紹介します。
副業では、雇用契約ではなく「業務委託契約」で仕事を請け負うケースがほとんどです。
しかし、契約書に書かれた内容をよく確認せずにサインしてしまい、「想定よりも業務範囲が広かった」「成果物に対する報酬が一方的に減額された」など、後から不利益を被るケースが後を絶ちません。
デザイン、ライティング、プログラミングなど成果物が発生する副業では、その「著作権」の取り扱いに注意が必要です。
契約書に何も定めがない場合、基本的に著作権は作成者に帰属しますが、相手側が「著作権も譲渡されたはずだ」と主張し、トラブルに発展することがあります。
納品後に「やっぱり不要になった」などと理由をつけられ、報酬を支払ってもらえないケースや、契約期間中にもかかわらず一方的に契約を打ち切られるトラブルも見られます。
特に口約束だけで仕事を始めてしまうと、後から条件を証明することが難しくなり、泣き寝入りせざるを得ないこともあります。
本業の会社によっては、副業に制限を設けている場合があります。
たとえば「競業禁止」や「事前申請制」などです。これを無視して副業を始めた結果、社内規定違反で懲戒処分を受けるリスクも存在します。
副業先との契約だけでなく、本業の就業規則にも十分に注意を払う必要があります。
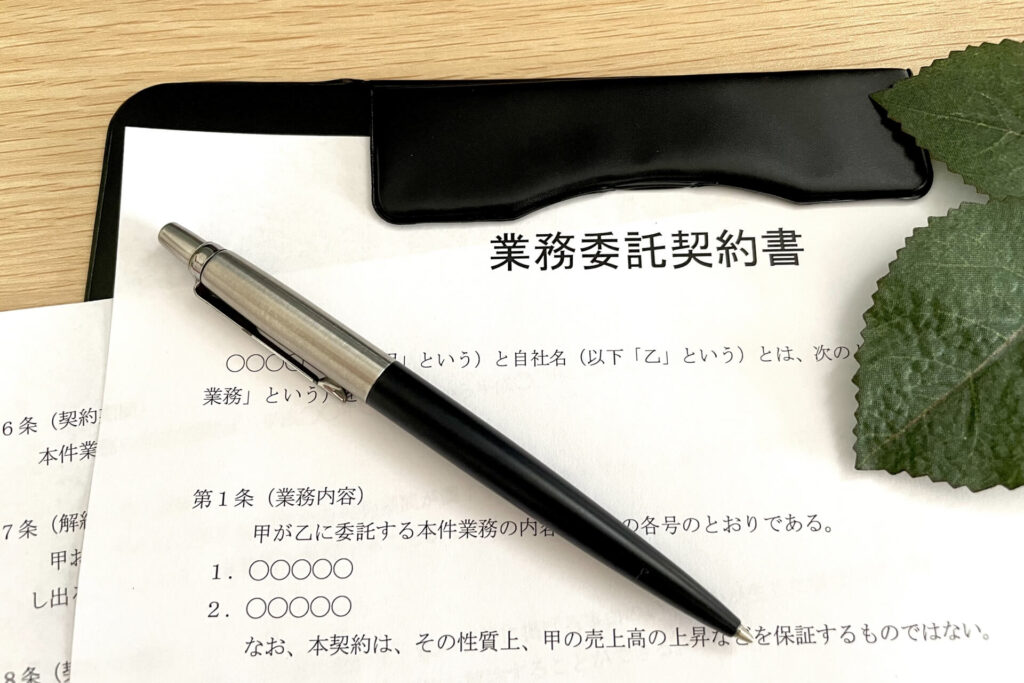
副業を安全に続けるためには、契約書をしっかりと確認し、自分に不利な条件が含まれていないかを見極めることが不可欠です。
ここでは特に押さえておきたい重要なポイントを紹介します。
副業では、正式な契約書を取り交わすケースが増えています。
面倒に感じるかもしれませんが、契約書は必ず全文に目を通しましょう。
業務内容・納期・報酬額・支払時期・契約期間などが具体的に記載されているかを確認し、不明確な表現があれば必ず相手方に確認を求めることが大切です。
デザインや文章、システム開発などの副業では、成果物の著作権に関する取り決めが重要です。
著作権が発生する仕事では、「著作権を譲渡するのか」「利用許諾にとどめるのか」によって、後々の扱いが大きく異なります。
著作権譲渡の場合、報酬額に見合った内容か慎重に検討しましょう。
「納品後〇日以内に振込」など、報酬の支払方法と支払期限は、契約書に明記してもらうことが基本です。
口頭のやりとりだけで進めると、万が一支払いが遅れた場合にトラブルに発展しやすくなります。
支払遅延時の対応(遅延損害金の設定など)も、場合によっては検討しましょう。
契約期間中に、一方的に契約を打ち切られてしまうケースも珍しくありません。
万が一、中途解約が発生する場合にどのような条件(たとえば事前通知義務、キャンセル料の有無など)が設定されているかを必ず確認し、不当な負担を負わされないよう注意が必要です。
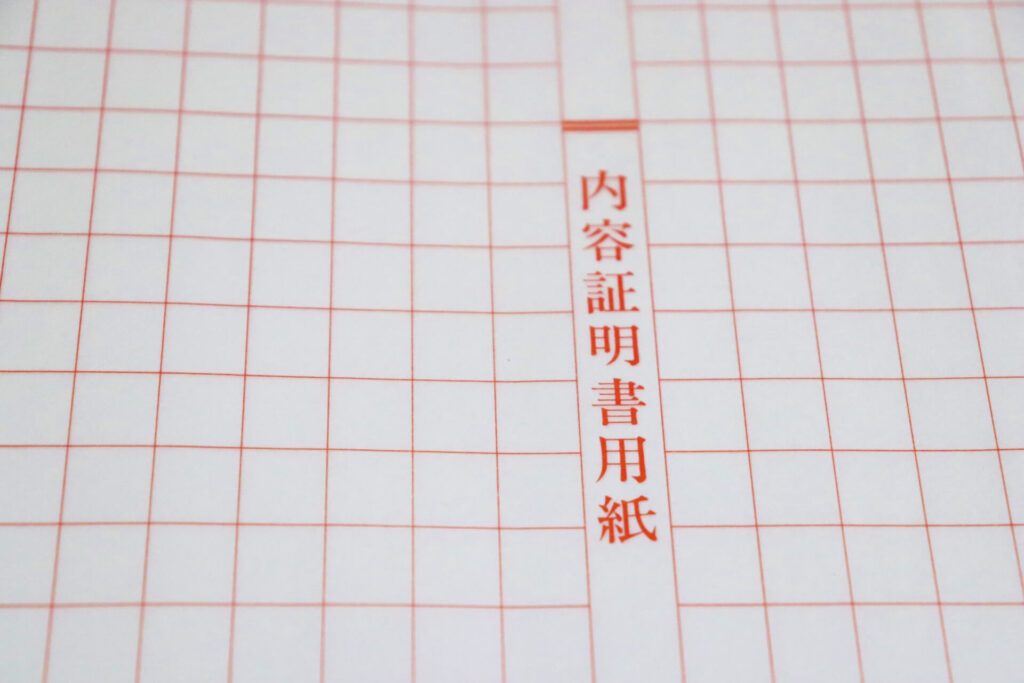
万が一、副業先とトラブルになった場合、感情的に動くのではなく、冷静かつ適切に対応することが重要です。
まずは「契約書」「業務の指示内容」「やり取りの履歴(メール、チャット、メッセージアプリなど)」をすべて保存しましょう。
証拠があれば、後の交渉や法的手続きにおいて自分の正当性を主張しやすくなります。
逆に、証拠がなければ泣き寝入りせざるを得ないリスクが高まります。
いきなり強硬手段に出るのではなく、まずは相手方に冷静に連絡を取り、事実確認と問題解決に向けた話し合いを試みましょう。
文書(メールなど)でやり取りを残しておくと、後々有利に働く可能性があります。
話し合いで解決できない場合は、内容証明郵便を送ることを検討しましょう。
内容証明郵便とは、「誰が」「いつ」「どんな内容の手紙を」送ったのかを郵便局が証明してくれる特別な郵送方法です。
これを送ることで、単なる口頭やメールのやりとりに比べて、はるかに強いプレッシャーを相手に与えることができます。
特に副業トラブルでは、
といったシーンで有効に機能します。
内容証明郵便を送るメリットは、大きく2つあります。
1つ目は、本気で争う意思があることを正式な形で相手に伝えられる点です。
これによって、相手が態度を改めたり、支払いに応じたりするケースが少なくありません。
2つ目は、万一、裁判などの法的手続きに発展した場合に、「この時点で正式に請求した」という事実を証明する有力な証拠になる点です。
内容証明は、弁護士に依頼して作成・発送してもらうこともできますが、自分で作成して郵便局から出すことも可能です。
ただし、文面の表現や請求内容によっては逆効果になることもあるため、不安な場合は専門家に相談してから進めるのが安心です。
個人の交渉で解決が難しい場合は、速やかに弁護士へ相談しましょう。
副業トラブルに詳しい弁護士であれば、交渉代理や裁判手続きまでスムーズに進められる場合があります。
早期に相談することで、被害を最小限に抑えることができます。

副業は、収入アップやスキルアップを実現する大きなチャンスですが、その裏には契約トラブルのリスクも潜んでいます。
契約内容を軽視してしまうと、報酬未払い、著作権問題、契約違反など、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうことも。
副業を安心して続けるためには、契約リテラシーを高め、トラブルの芽を事前に摘み取る意識が欠かせません。
もし副業トラブルに巻き込まれてしまった場合でも、あわてず証拠を集め、冷静に対応することが大切です。
一人で解決が難しいと感じたら、早めに専門家へ相談しましょう。
自分の身を守りながら、副業ライフを充実させていきましょう!

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。