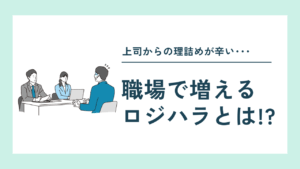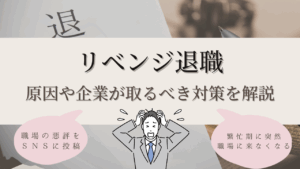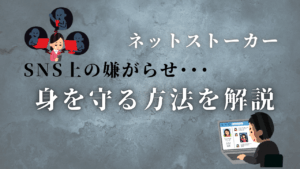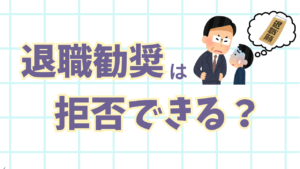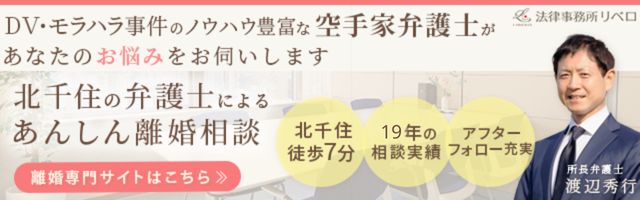
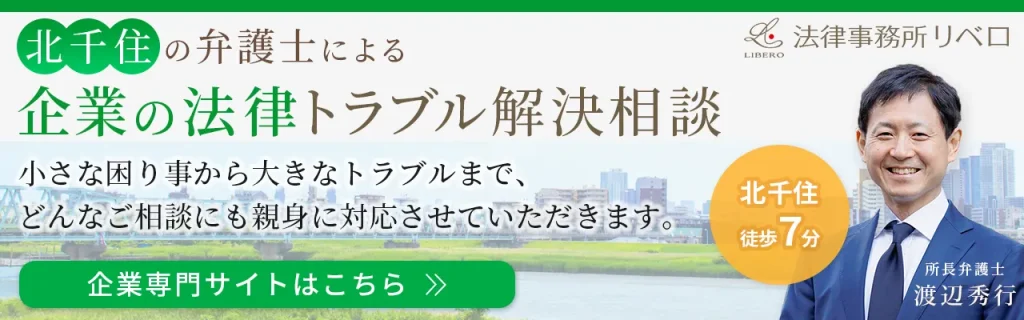
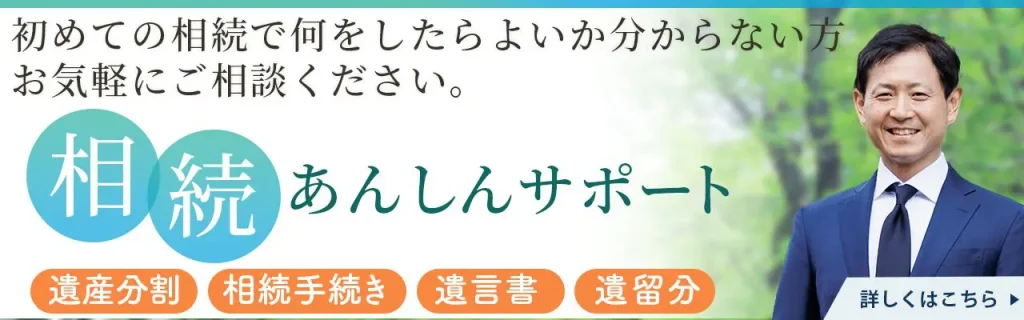
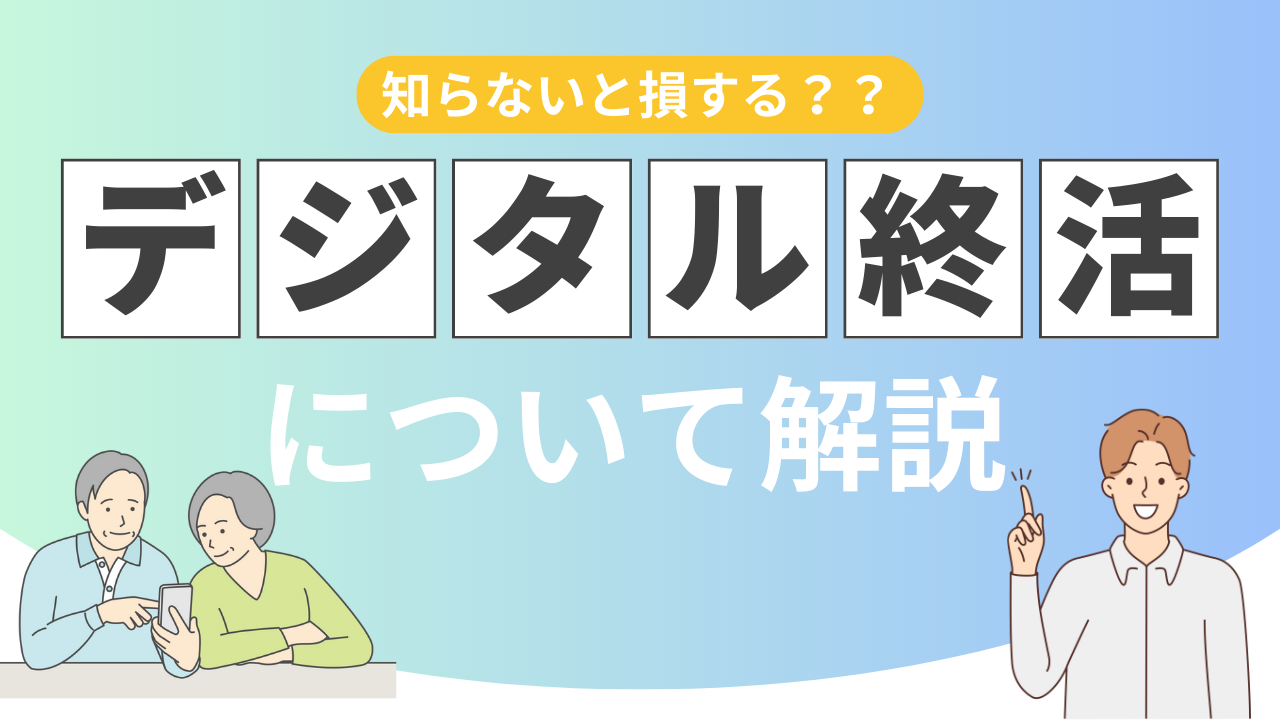

法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
近年,人生の終わりに備えて「終活」を行う人が増えています。
しかし,意外と見落とされがちなのがインターネットやスマホを通じて利用しているデジタル資産・遺産の整理です。
ネット銀行や証券口座、暗号資産(仮想通貨)といった財産はもちろん,SNSのアカウントやクラウドに保存された写真,動画配信や音楽アプリなどのサブスク契約まで,私たちの生活は多くのデジタルに支えられています。
これらを放置したまま亡くなってしまうと,遺族はログインできずに財産を引き継げなかったり、解約できずに費用だけが発生し続けたりするリスクがあります。
実際に「暗号資産のパスワードが分からず数百万円が宙に浮いた」「亡くなった親のSNSがそのまま残り、なりすまし被害に遭った」といったトラブルも少なくありません。
こうした問題を防ぐために注目されているのが“デジタル終活”です。
デジタル終活とは,生前のうちに自分のデジタル資産や利用サービスを整理し,家族が円滑に引き継げるように備えることを指します。
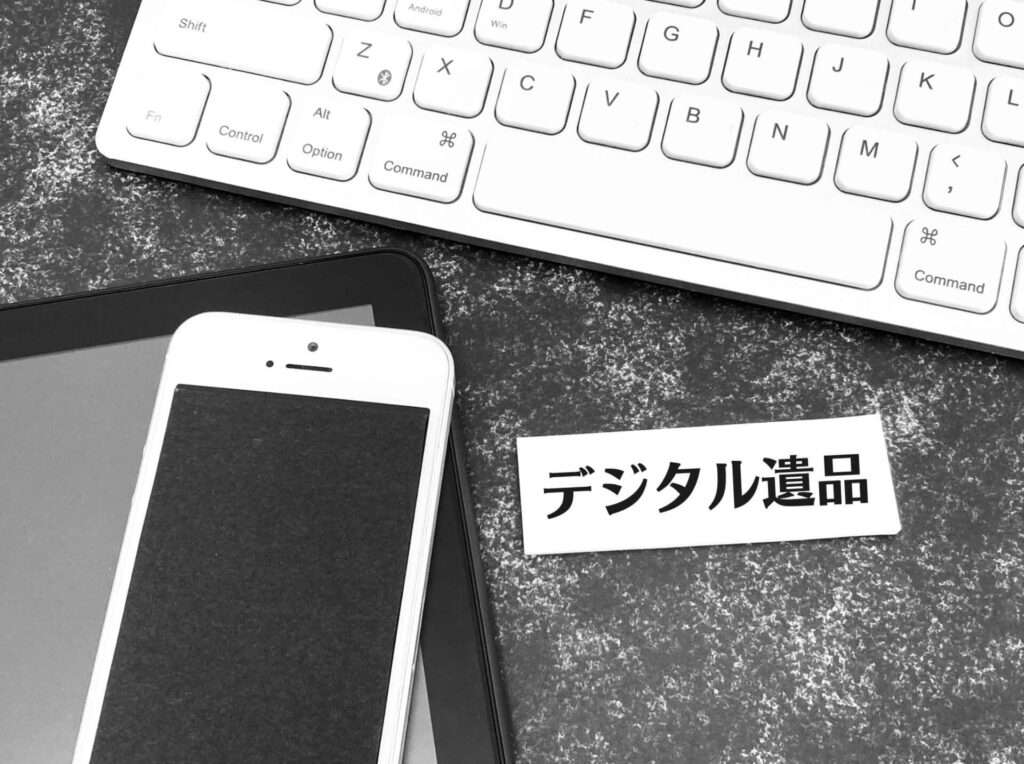
「デジタル遺産」とは、亡くなった人が生前に使っていたインターネット上の資産やデータのことを指します。
従来の相続では現金や不動産、株式といった“目に見える財産”が中心でしたが、今ではスマホ1台にさまざまな価値が詰まっており、見えない財産=デジタル資産・遺品への注目が高まっています。
但しすべてが相続財産として法的に明確なわけではありません。
たとえば、ポイントサービスやSNSのアカウントは、利用規約で本人死亡時に消滅と定められていることもあり,相続できるかどうかは個別判断になります。
また,パスワードが分からなければ、たとえ相続できる財産でも実際には引き出せないという問題も発生します。
このように、デジタル資産・遺品は“相続できるかどうか”と“技術的にアクセスできるかどうか”の両面で注意が必要なのです。

デジタル遺産の相続では、「存在はわかっているのに手続きできない」「気づかないまま放置されて損害が出る」といったトラブルが頻発しています。
ここでは代表的な事例をいくつか紹介します。
デジタル資産を生前に整理せず放置することで発生する大きなトラブルは,財産が失われてしまうことです。
たとえば暗号資産やネット銀行口座はIDやパスワードがなければアクセスできません。
相続人がその存在を知っていたとしても,ログイン情報がなければ残高を確認することさえできず,数百万単位の財産が誰も触れないまま失われていくといったケースが想定されます。
SNSのアカウントはデジタル遺産に分類されます。
もし亡くなった後,SNSのアカウントが放置されれば,故人の名前や写真がインターネット上にそのまま残ってしまいます。
これにより,第三者によるなりすましやアカウントの不正利用の被害が発生する可能性も考えられます。
万が一故人のSNSが不正利用された場合,遺族にとっては精神的負担も大きく,はやくアカウントを閉鎖したいが手続がわからない・・・と悩むことでしょう。
サブスクリプション契約などの自動で課金されてしまうインターネット上の契約をそのままにしておくと、亡くなった後も利用料が引き落とされ続ける可能性があります。
このようにデジタル遺産を放置すると,金銭的な損失だけでなく,なりすましや不正アクセスなどの二次被害,さらには遺族の精神的負担まで生じることとなります。
現代における相続の新しいリスクとして,デジタル終活を進めておく重要性はますます高まっているのです。

では,デジタル終活は生前にどのようなことを行えばよいのでしょうか?
すぐに実践できるものを以下に紹介します。
もっとも手軽な方法は,パスワード管理アプリの利用です。
代表的なアプリでは複雑なパスワードを一元管理でき,マスターパスワード1つで情報を引き出すことができます。
これをエンディングノートや遺言書と併用すれば,家族が必要なときにスムーズにアクセスできます。紙に書き残す場合は,必ず金庫や貸金庫など安全な場所に保管し,信頼できる家族や専門家に存在を伝えておきましょう。
また,複数のサービスで同じパスワードを使っている場合,一度漏れてしまうと他のアカウントまで危険にさらされます。
デジタル終活を進めるタイミングで、パスワードの見直し・強化を行うことも有効です。
動画配信や音楽アプリ,オンラインストレージなどのサブスク契約は,利用者が亡くなっても自動的に解約されるわけではありません。
そのまま放置すれば利用料が引き落とされ続け,遺族に余計な負担をかけることになります。
そこで,生前に利用中のサービスをリスト化し,契約先や解約方法をまとめておくと安心です。
特にスマホアプリ経由で契約しているサービスは,家族が存在自体に気づかないケースも多いため,早めの整理が欠かせません。
デジタル資産の中でも,暗号資産やネット銀行口座,ネット証券の残高などは明確に相続財産として扱われます。
これらを誰に引き継ぐのかを定めるには,遺言書が最も確実な方法です。
自筆証書遺言でも可能ですが,改ざんや紛失のリスクを考えると,公正証書として残しておく方が安心といえるでしょう。
暗号資産は相続税の課税対象となる点も忘れてはなりません。
財産の内容や相続人の関係に応じて,弁護士や司法書士に相談しながら法的に有効な形で記載しておくことが望ましいでしょう。

デジタル終活は自分で工夫して進められる部分も多いですが,実は法律上の落とし穴がいくつか存在します。
ここを理解していないと「良かれと思って準備したのに、逆にトラブルになった」という事態にもなりかねません。
まず注意すべきは,IDやパスワードの取り扱いです。
生前に家族へ直接伝えてしまうと,相続が始まる前に第三者がログインする形となり,不正アクセス禁止法に抵触するおそれがあります。
契約者本人の死後に相続人が正当に引き継げる形にしておくことが重要です。
そのため,パスワードをそのまま共有するのではなく,エンディングノート等の書類に記載しそれを金庫に保管する等,必要なときに開示できる仕組みを整えておくことが推奨されます。
不正アクセス禁止法とは、他人のIDやパスワードを使って無断でログインする行為を禁じる法律です。たとえ家族や親しい間柄であっても、本人の生前に承諾なく利用すれば違法となる可能性があります。
次に、暗号資産やネット銀行口座の扱いです。これらは相続財産に含まれるため,相続税の課税対象となります。
相続人が存在や残高を把握できないと,申告漏れのリスクにつながり,後に税務調査で追徴課税を受ける可能性もあります。
必ず遺言書や資産リストに記載し,相続人に正しく伝えられるようにしましょう。
さらに,SNSアカウントやメールなどのデータは,財産的価値はない場合でも「個人情報」として扱われます。
勝手にログインして削除や編集を行うと,法的な問題が発生する可能性もあります。
このように,デジタル終活には独自の法的リスクが存在します。
自己流の対応では不十分なことも多いため、最終的には専門家に相談して準備を進めるのが安心です。

デジタル資産・遺品は目に見えないがゆえに,放置すると存在すら気づかれず消えてしまう財産や解約できない契約となり,遺族に金銭的・精神的な負担を残します。
SNSのなりすましや不正利用など,思わぬトラブルにつながるケースも少なくありません。
こうしたリスクを防ぐためには①ID・パスワードの適切な管理,②サブスク契約の解約準備,③遺言書への記載といったステップを踏むことが大切です。
特にパスワードの取り扱いや暗号資産の相続は,法律上の注意点も多いため専門家のアドバイスを受けながら進めると安心です。
デジタル終活は一度に完璧に整える必要はありません。
まずは自分の利用しているサービスを書き出すなど,小さな一歩から始めてみることが現実的です。
その積み重ねがご自身の財産を守り,ご家族の負担を減らすことにつながります。
これからの時代,デジタル終活は「特別な人が行う相続」ではなく,誰にとっても必要な終活の一種となりました。
早めに取り組むことで,安心して未来を迎えることができるでしょう。

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。