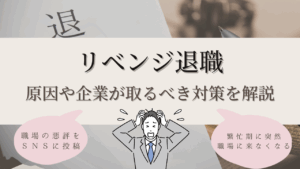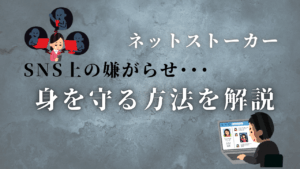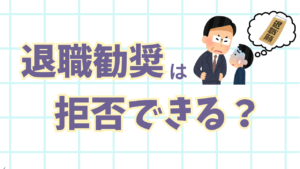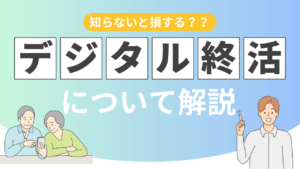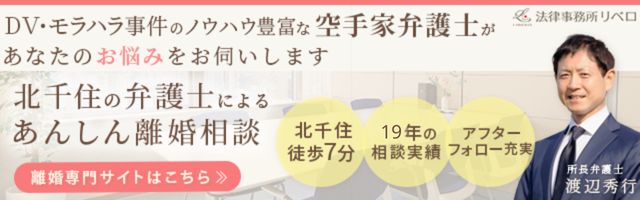
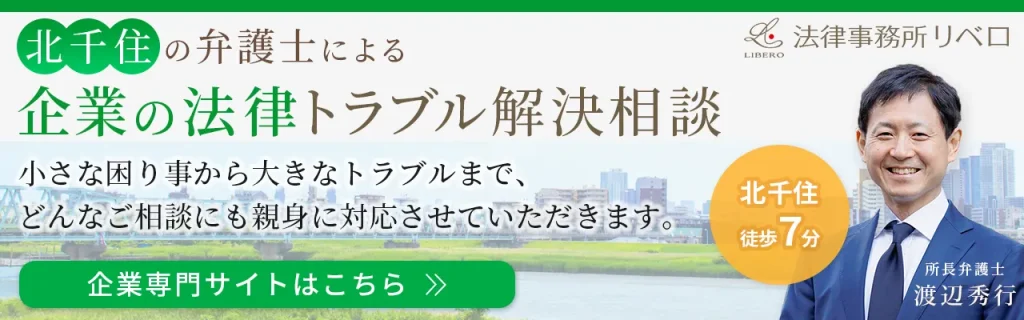
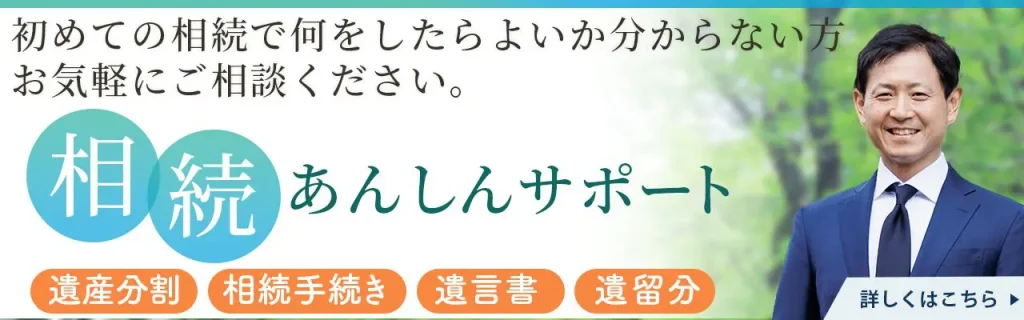
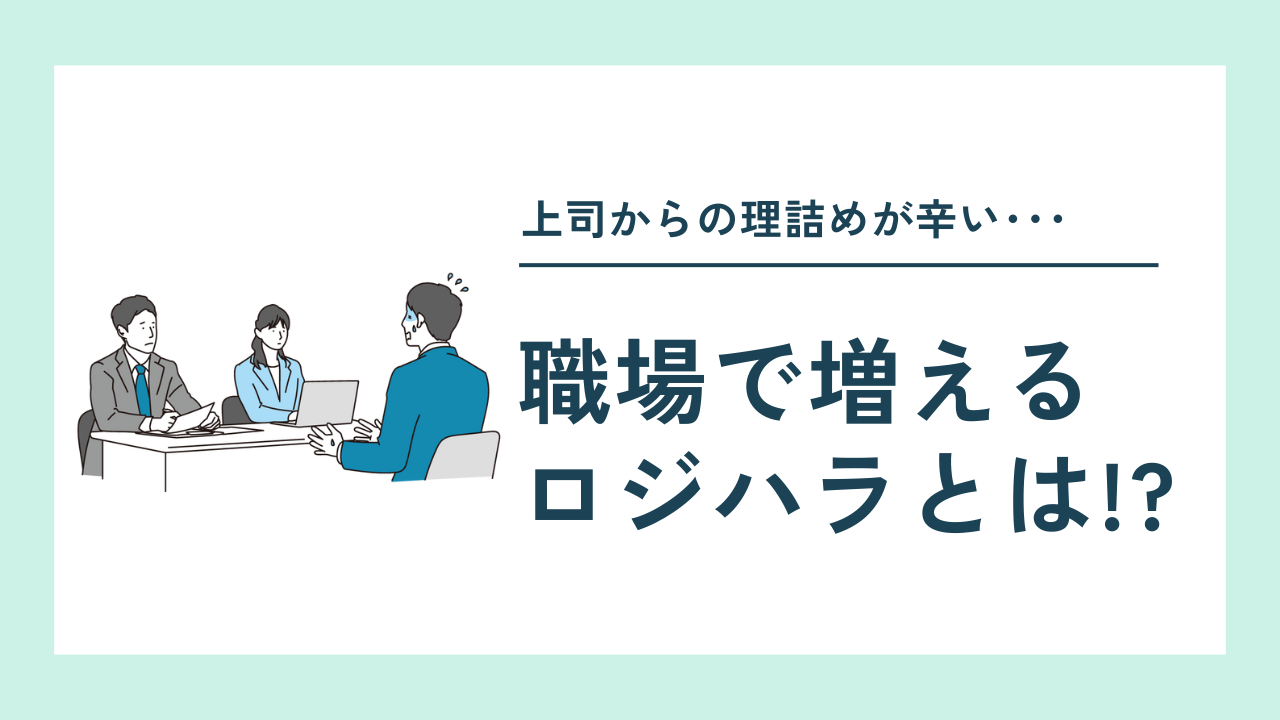

法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
職場で,どんな話題でもすぐに論破してくる上司に悩まされている人は少なくありません。
発言者が一生懸命プレゼンテーションを行っても「その案は現実的ではないよね?」「根拠はあるのか?」と返され,最終的には何も言えなくなってしまう・・・。
このような言動は“ロジカルハラスメント(通称:ロジハラ)”に該当する可能性があります。
上司の指摘は,一見理論的で正しいようにも聞こえますが,発言する部下は常に緊張を強いられ,自分の意見がすべて否定されることから強いストレスや無力感を感じるようになります。
本記事では論破してくる上司の言動をどのように捉えるべきか,そして「モラハラ」と「発達障害」の境界線をどこに引くべきかを解説します。

最近よく耳にするようになったロジカルハラスメント(以下ロジハラといいます)とは,
論理的思考を振りかざして,相手を追い詰めるようなコミュニケーションをとることを指します。
一見すると「正論を言っているだけ」「間違ったことは言っていない」と捉えられてしまうため,周囲からもハラスメントと思われにくい点が非常に厄介です。
たとえば部下がミスを報告した際に
「それはどうして起きたの?原因は?普通は○○するよね?それを防ぐ手立てはおもいつかなかったの?」などと矢継ぎ早に問い詰め,その回答が曖昧だと「だからだめなんだよ・・・」と切り捨てる。
言っている内容自体は筋が通っているように見えても,会話のキャッチボールが成立せず,常に論破される側が萎縮していく,これがロジハラの典型例です。
ロジハラの本質は論理そのものではなく,論理の使い方にあります。
相手を理解しようとするのではなく,相手を打ち負かすための道具として論理や理屈を使うことが問題なのです。
こうした言葉の使い方や相手を問い詰める行為はモラハラの一形態とも重なります。
モラハラ加害者は感情ではなく理屈で相手を支配することがあります。
このように正論を盾にして,相手の意見や気持ちを封じ込めていくのです。
現代の職場ではロジカルシンキングやエビデンスベースといった言葉が重視される傾向にあります。
その結果,感情を排して理論的に話すことが正義とされる文化が生まれました。
しかしこの風潮が行き過ぎると,共感や尊重が欠けた冷たいコミュニケーションになりがちです。
実際に,ロジハラをしてしまう上司の多くは,相手を傷つけているという自覚がありません。
むしろ「自分は教育している」「改善を促すために言った」と思いこんでいるケースが多いのです。
この無自覚な加害こそがロジハラを根深い問題にしています。

論破をする上司の中には発達障害(特にASD=自閉スペクトラム症)の傾向が見られる場合もあります。
ASDの傾向がある場合は上記のような特徴があり,本人に悪意がなくても結果的に“冷たい態度で理詰めにする人”という風に他人から映ってしまうことがあります。
ASDの傾向がある人は事実やルールに基づいて考えることを得意とします。
例えば,部下がミスをした時「なぜこうなったのか?どの手順が間違っていたのか」と淡々と分析しようとします。
上司としては感情を排した正しい対応をしているつもりですが,受け手からすると「責められている・・・」と感じることも少なくありません。
さらに,言葉のニュアンスや相手の気持ちを読み取ることを苦手としているため,意図せず理詰めや論破をしてしまうこともあります。
つまり,相手を傷つけようとしているのでなく,単に論理的に話しているだけというケースもあるのです。
先に述べたとおり,発達特性のある上司は相手を理解することが困難なため,事実を分析して整理をした結果,論理的に話してしまいます。
一方でモラハラ上司は相手を支配・否定して自分が優位に立ちたいという目的で相手を論破します。
そのため,同じ“論破”という行為でも,背景にある動機が全く異なるため論破してくる上司=モラハラとは一概には言えないのです。
上司に発達障害の可能性がある場合には,職場全体での理解が必要です。
例えばコミュニケーションの取り方を工夫したり,業務の進め方を可視化することで,摩擦を減らすことが出来ます。
逆に相手が意図的に攻撃してくるようであれば,それはハラスメントとして対処する必要があります。

ロジハラは上司と論破された部下の関係だけでなく,職場全体の人間関係や組織の機能に深刻な影響を及ぼします。
ロジハラ上司の下では,会議や報告の場が「意見を出す場」ではなく「正誤を競う場」になりがちです。
発言する度に細かく論理の矛盾をつかれ,根拠は?それは実現できるか?と詰められてしまうと
部下達は間違えるリスクを避けるようになり,発言しない・上司に意見を言わない文化が根付いてしまいます。
最初は1人の被害者だったものが,やがて周囲が何も言わずに見過ごすようになり,最終的に上司の態度が許される空気になってしまうのです。
心理的安全性とは組織内で自分の意見を言っても大丈夫だと思える状態を指します。
ロジハラが続く職場ではこの心理的安全性が失われます。
上司の前で意見を述べれば論破され,ミスを報告すれば原因追及が始まる。
そのため部下たちは防衛的になり,報告や相談が遅れるようになります。
特に若手の社員は「どうせ何を言っても否定されてしまう」と感じ,早期離職に繋がるケースも少なくありません。
その結果,ロジハラ上司の下では人材が定着しないという悪循環が生まれます。
ロジハラの問題点は周囲が「上司の意見は論理的で正しい」と思い込んでしまうことです。
論理的は言葉や話し方は説得力を持つため,表面上は筋が通って見えます。そのため,第三者からすると「上司の言っていることは間違ってないのでは?」と誤解されやすいのです。
そのため部下は,論破されたことや周囲の理解を得られなず「自分が悪い」「能力が足りない」と感じ自己否定を深めていきます。
ロジハラの怖さは,モラハラ・パワハラのように人格否定を行ったり,怒鳴ったりする行為がなく目立たない点です。
声を荒げることなく静かに部下の精神を削っていくため,上層部がこの問題に気づいたときには,すでにチームが崩壊していることも少なくありません。
報告・連絡・相談の停滞,ミスの隠蔽,離職率の上昇など,ロジハラは職場に様々な悪影響を及ぼすのです。

ロジハラは一見正しい指摘や業務上の指導に見えるため,周囲も対応しづらい点が厄介です。
しかし,この問題を放置すれば,組織の信頼関係が壊れ,優秀な人材が次々と離れていくことになります。
ここでは,立場毎にとるべき具体的な対応について述べます。
まず重要なことは,納得させられる報告やプレゼンができなかった自分が悪いと思い込まないことです。
ロジハラ気質の上司の言葉は,一見理屈が通っているように見えても,人格や価値を否定するような論理展開が繰り返されていれば,それは正当な指導とは言えません。
次に上司とのやりとりの記録を残すことも大切です。
メールやチャット,会議の議事録など具体的な発言内容や日時をできるだけ客観的に残しておきましょう。
録音が可能な環境であれば,声のトーンや言葉選びも証拠として有効になります。
また社内のハラスメント相談窓口や,労働局・弁護士など外部の専門家へ相談することも検討しましょう。
自分1人で抱え込まず,第三者の視点を入れることで事態の深刻さを冷静に判断できることがあります。
ロジハラの被害者は,自分がハラスメントを受けていることを自覚できないケースがあります。
もし同僚が上司から理詰めにされ,精神的に追い込まれているようであれば,「あの指摘の仕方はおかしい」と声を上げることが大切です。
しかし,直接的に上司を非難するのはリスクが大きいため,
「○○さん,最近元気がないように見える」「会議でのやりとりで,すこし言い方がきついように感じた」
など,事実ベースで人事部や相談窓口へ伝えることが望ましいといえます。
沈黙や傍観は結果としてロジハラを容認することに繋がります。周囲の勇気ある一言が,被害をくいとめるきっかけになるのです。
企業側には,ハラスメントを防止し,従業員の心理的安全性を守る法的義務があります。

まず,管理職研修などで“ロジハラ”の具体例やそのリスクを共有し,指導とハラスメントの違いを理解させることが重要です。
また相談しやすい環境を整えることで被害を早期に把握できます。

ロジハラを防ぐために必要なことは,部下の意見を正すことではなく尊重することです。
どれほど理にかなった正しい意見であっても,しつこく質問攻めにしたり意見を否定して部下を追い詰めたり,人格を否定するような伝え方をすれば,それは指導ではなくハラスメントになってしまいます。
大切なことは,相手の理解度や感情に配慮しながら,建設的なコミュニケーションを心がけることです。
職場で意見が対立したときこそ,「どうすれば伝わるか,どうすれば協力し合えるか」という視点を持つことが,ハラスメントの防止に繋がります。
論破よりも対話すること,部下の意見を尊重すること,この意識の積み重ねが,安心して意見を交わせる職場づくりに繋がることと思います。

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。
法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。